「CT検査って何分かかるんですか?」~技師が患者さんに伝えられないこと~
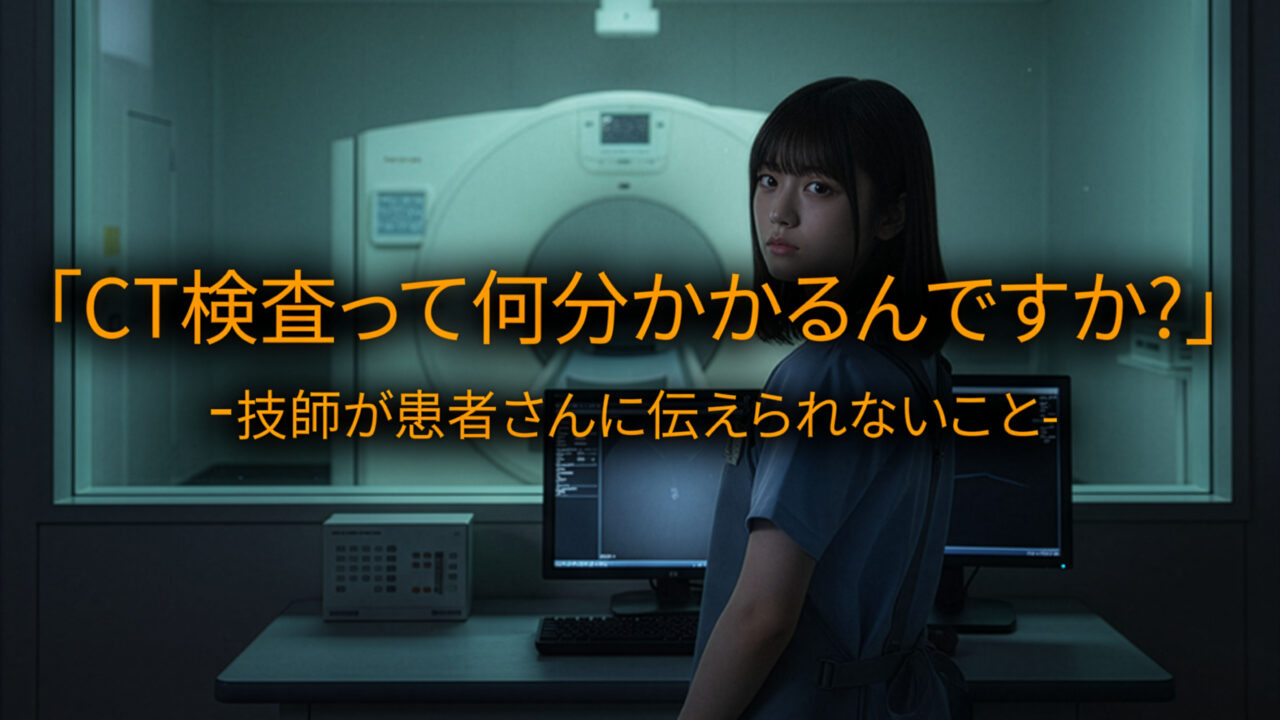
検査室の時計は患者さんと違う時間を刻む
「何分くらいで終わりますか?」
よく聞かれる質問です。放射線技師歴十数年の私は、この質問に答えるとき、いつも少し違和感を覚えます。
「10分です」—— これは撮影時間。でも患者さんが知りたいのは、それじゃない。
第1部 時間認識のズレ
「10分」の正体
先日、60代の女性患者さんが検査後にこう言いました。
「30分って聞いてたのに、1時間かかったわ」
カルテを確認すると、撮影時間は8分。
実際の内訳:
- 更衣室で服を脱ぐ:5分
- 待合室で呼ばれるまで:10分
- 撮影:8分
- 検査後の説明:3分
- 着替え直す:5分
- 合計:約40分
私たちが「検査時間」と呼ぶのは撮影時間のみ。患者さんにとっての「検査」は、名前を呼ばれた瞬間から始まっている。
このズレは、説明の仕方を変えるだけで減らせる。「撮影は10分ですが、着替えなど含めて40分ほどお時間いただきます」—— こう言うだけで、クレームは減ります。
検査の種類で変わる時間
単純CT(造影剤なし)
撮影:5分 / 検査室:10分 / トータル:30-40分
造影CT(腹部・胸部)
撮影:10分 / 検査室:15-20分 / トータル:45-60分
心臓CT(冠動脈CT)
撮影:15分 / 検査室:25-30分 / トータル:60-90分
病院のHPには「10-15分」と書いてある。間違いじゃない。でも、患者さんが体感する時間とは違う。
第2部 「ただ寝てるだけ」という誤解
息止めの難しさ
「検査中は横になって寝ているだけです」—— 病院サイトでよく見る表現。
でも実際は、息を吸って5〜10秒止める。また吸って、5〜10秒止める。これを3回程度繰り返す。
そのたびに、臓器が微妙に動く。肺が膨らむと肝臓が下に押される。胃も腸も、数ミリ位置が変わる。
「毎回同じくらいの大きさで息を吸って下さい」と指示を出すが、大抵の患者さんは同じ位置で息を止めることができない。
人間の体は、同じ息の吸い方を2回することができない。これに気づいたのは、画像を見ながら「スキャンの位置は同じなのに、なんで毎回肝臓の位置が違うんだろう」と悩んでいたときです。
【息止めの理想と実際】
各回とも同じ深さ・同じ長さで息を止める
画像のブレがなく、診断精度が向上します
深さも長さもバラバラ
画像のブレや診断の精度低下につながる可能性があります
ポイント
- 同じように息を吸ったつもりでも、毎回微妙に違う
- これが画像のブレにつながることも
- 技師の指示通り、できるだけ同じ深さで息を吸うことが大切
- 不安な場合は、検査前に練習することもできます
造影剤の「あの感覚」
造影剤を入れると、体が熱くなります。
メカニズム:
- 造影剤は検査前に37℃前後に保温してある
- それを急速注入(2-5ml/秒)で静脈に入れる
- 造影剤の浸透圧が血液より高い(約2倍)
- 浸透圧を等しくしようとして血管が拡張
- 血流量が増え、熱感として感じる
「下半身が温かくなりますが、20秒ほどで消えます」と説明しても、実際に感じるまで想像できない人がほとんど。
患者さんの表現:
- 「お風呂に入ったみたい」
- 「体の中から火がついた」
- 「おしっこ漏れたかと思った」(実際は漏れていません)
同じ造影剤でも、体感は全員違う。言葉と体感のズレは、どう説明しても埋まらない部分がある。
【CT検査別の造影剤使用量】
注意事項
- 基本的に体重や撮影方法で造影剤量を調整します
- 心臓CTは血管が細いため、濃度も高めの造影剤を使用
- その分、体が熱く感じる度合いも強い
第3部 患者さんが見えない技師の仕事
検査室の外にいる理由
撮影中、私たちは操作室に移動します。
ある時「一人にしないでほしい」— と言わたことがあります。
でも、私が外にいるのは被ばくから自分を守るため。年間数線件以上の検査を担当していたら、積算線量が問題になる。
患者さんには見えないこと:
- ガラス越しにずっと見ている
- 心電図モニターをチェックしている
- インターホンで常に会話できる状態
- カメラで動きを確認している
「見えないけど、つながっている」— これを伝えるのが難しい。
「異常ありますか?」に答えられない葛藤
検査後、よく聞かれます。「何か見つかりましたか?」
答えられないんです。
画像を「撮る」のが技師の仕事。「診る」のは医師の仕事。
ときどき、明らかに大きな影が見えることがある。でも、それが何なのか、私には言えない。言ってはいけない。
これが、技師として一番つらい瞬間です。
第4部 検査前に確認すること
服を脱ぐ基準
脱ぐ必要がある
胸部CT、腹部CT、骨盤CT
理由:ボタン、ファスナー、ブラのホック、ベルトの金具がアーチファクトを起こす
そのままでOK
頭部CT(ヘアピン、ネックレスは外す)
患者さんによっては「念のため脱ぎます」という人もいれば、「これくらい大丈夫でしょ」と金属付きベルトのまま来る人もいる。感覚のズレは、説明してもゼロにはならない。
造影剤が使えない人
- 腎機能低下 (eGFR <30ml/min/1.73m² が目安)
- 喘息の既往 (副作用リスク約10倍)
- 過去に造影剤アレルギー
- ビグアナイド系糖尿病薬の服用中
「腎機能が低下」は患者さん自身では分からないことが多い。だから検査前に血液検査でクレアチニン値をチェックする。
副作用の確率(病院によってバラつきあり)
【造影剤副作用の確率を日常と比べると】
2-5%
100人に2-5人
雨の日に傘を忘れる確率と同じくらい
0.025-0.1%
1,000人〜4,000人に1人
1年間で交通事故に遭う確率より低い
0.001%
10万人に1人
落雷に当たる確率と同じくらい
- ただし、喘息のある人は副作用リスクが約10倍
- 数字は統計によって幅があります
なぜ病院によって数字が違うのか? 使っている造影剤の種類、患者層、統計の取り方が違うから。
「確率が低い」と言われても、自分がその「1人」になるかもしれない不安は消えない。そこは技師も理解している。
私も造影CT検査を受けたことがありますが理解が深いだけにドキドキでした。
第5部 検査後の指導
水分摂取の具体的な量
「たくさん水を飲んでください」—— これだと曖昧。
私は「いつもより500mlくらい多めに」と具体的に言うようにしています。
造影剤の排出:
- 6時間で80%
- 24時間でほぼ全量
ただし、心不全や腎不全で水分制限がある人は、主治医の指示が優先。
主に腎臓から尿として排泄されます。
投与後6時間以内: 投与量の約80~90%以上が排泄。
投与後24時間以内: 投与量の約95~99%が排泄。
~イオメロン350注シリンジの取説より抜粋~
遅延性副作用
検査後、数時間〜数日後に発疹やかゆみが出ることがあります(稀)。
「検査の時は何ともなかったのに」と驚く患者さんも多い。症状が出たら、遠慮せず検査を受けた病院に連絡してほしい。
最後に 技師として伝えたいこと
CT検査について調べると、どのサイトも似た情報が並んでいます。
「痛みはありません」「短時間で終わります」「安全な検査です」
全部本当。でも、それだけじゃない。
検査台の上で息を止める10秒は、日常の10秒より長く感じる。
造影剤が入る瞬間の熱さは、説明を聞いていても驚く。
一人で検査室に残される時間は、2分でも不安。
これは、数字や説明だけでは伝わらない。
私が現場で学んだこと。それは、検査は技術だけじゃ成り立たないということ。
高性能なCT装置があっても、患者さんが緊張で体を動かしてしまったら、診断に使える画像は撮れない。
だから私たちは毎日、「どう説明したら安心してもらえるか」を考えている。
技術だけでなく、コミュニケーション。これが、患者さんには見えない技師の仕事です。
診療放射線技師より
【医療人向けクイズ】あなたは放射線技師?
A. 室温(20-25℃)
B. 人肌(35-37℃)
C. 常温保存で加温不要
答え: B
造影剤は粘稠度を下げて注入圧を抑えるため、また急激な冷感を避けるため、35-37℃に保温して使用します。保温器(ウォーマー)で管理するのが一般的。
A. 70回/分以下
B. 65回/分以下
C. 60回/分以下
答え: C
理想は60回/分以下。最新の装置でも、拡張期の静止期をしっかり確保するにはこの心拍数が望ましい。ただし、患者の状態によっては65回/分程度でも撮影可能な場合もある。
A. アレルギー性(蕁麻疹)
B. 化学毒性(熱感)
C. 血管迷走神経反射
答え: B
熱感は化学毒性によるもので、ほぼ全員に起こる正常反応。アレルギー性の副作用(蕁麻疹など)は100人に2-5人程度。血管迷走神経反射はさらに稀。



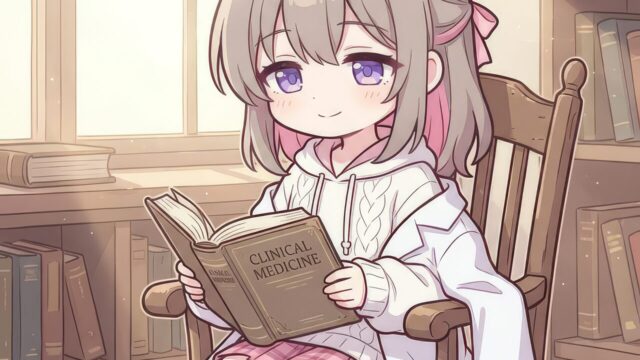


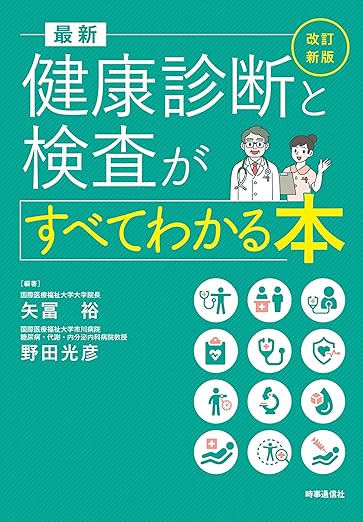
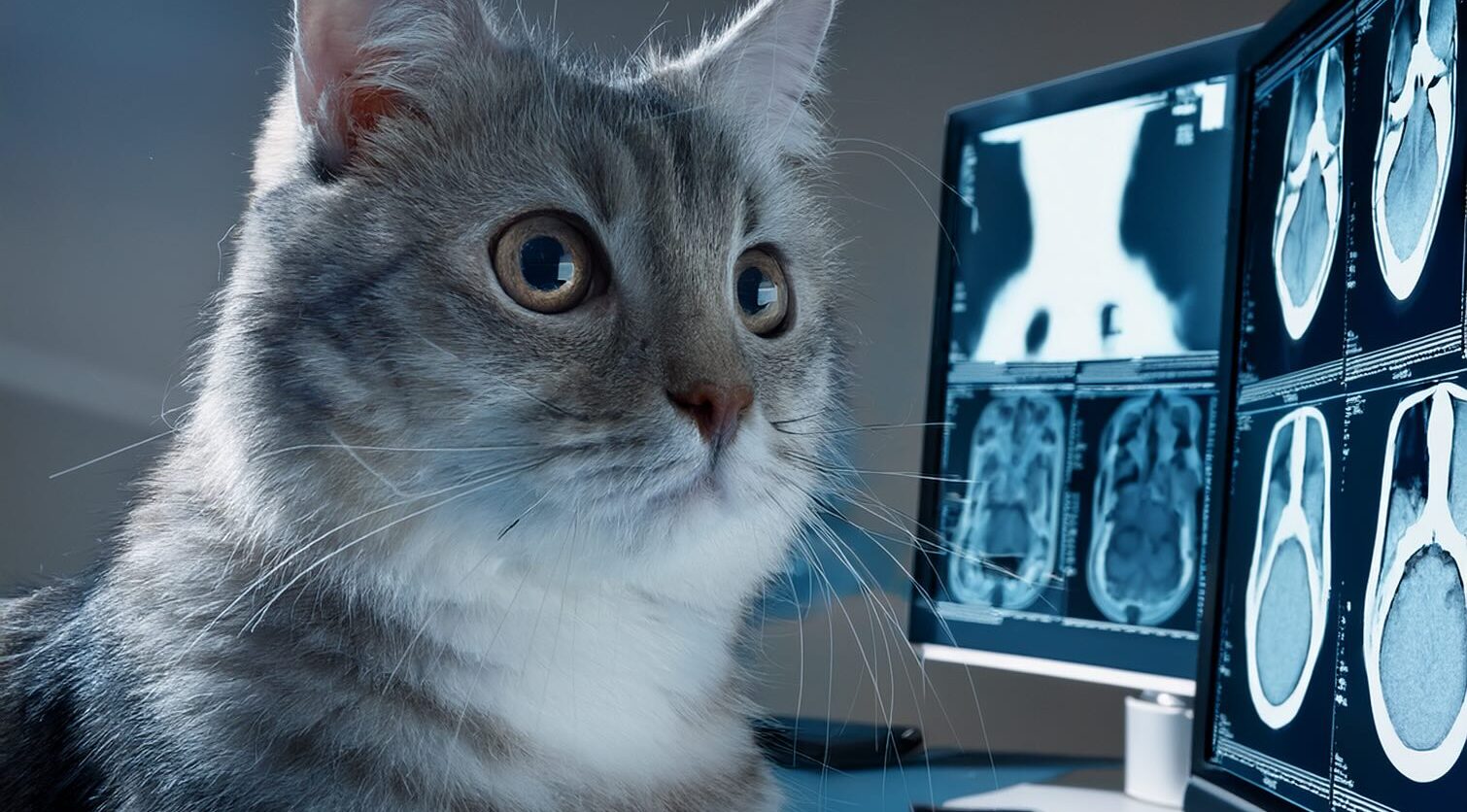







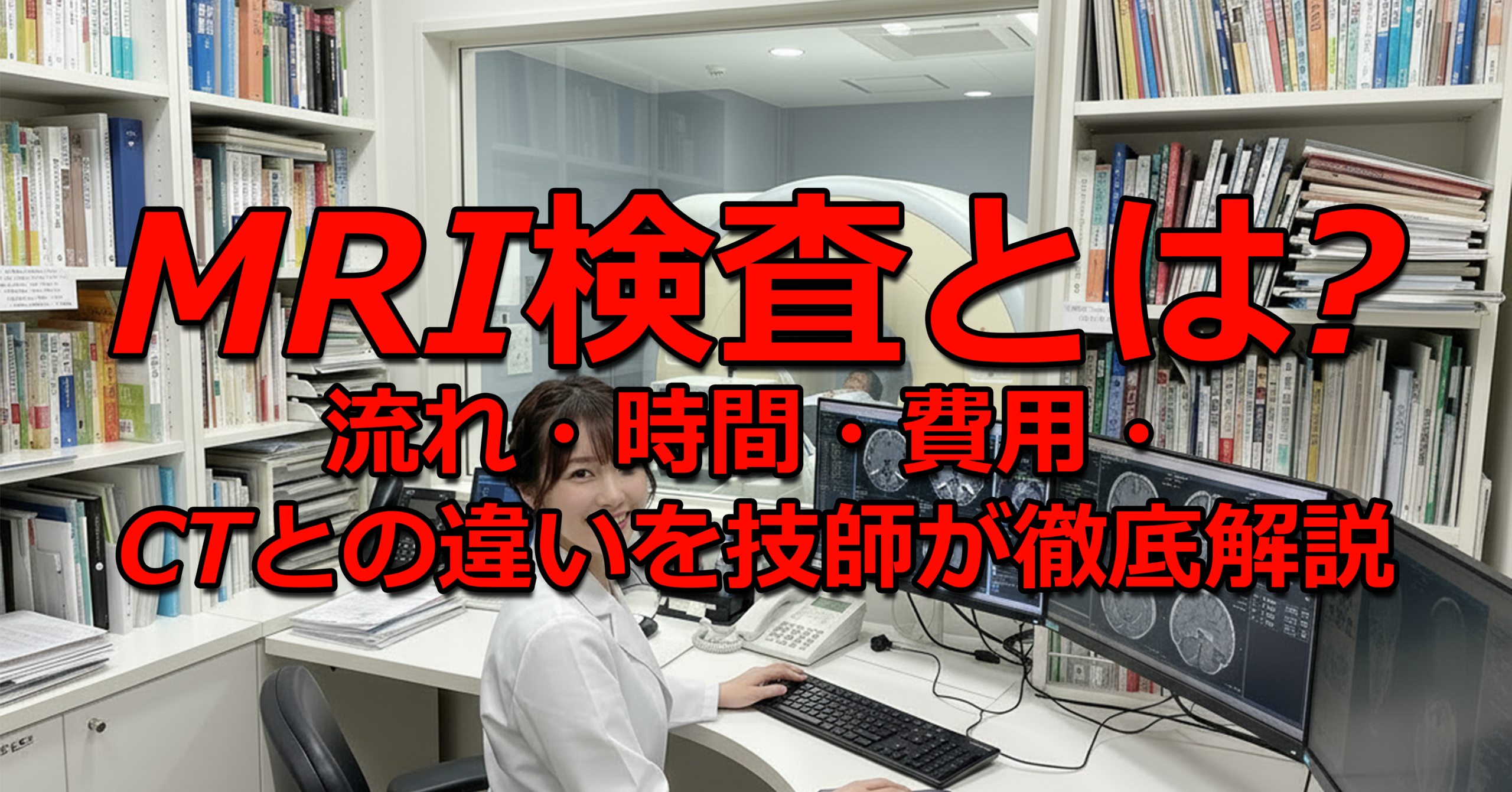
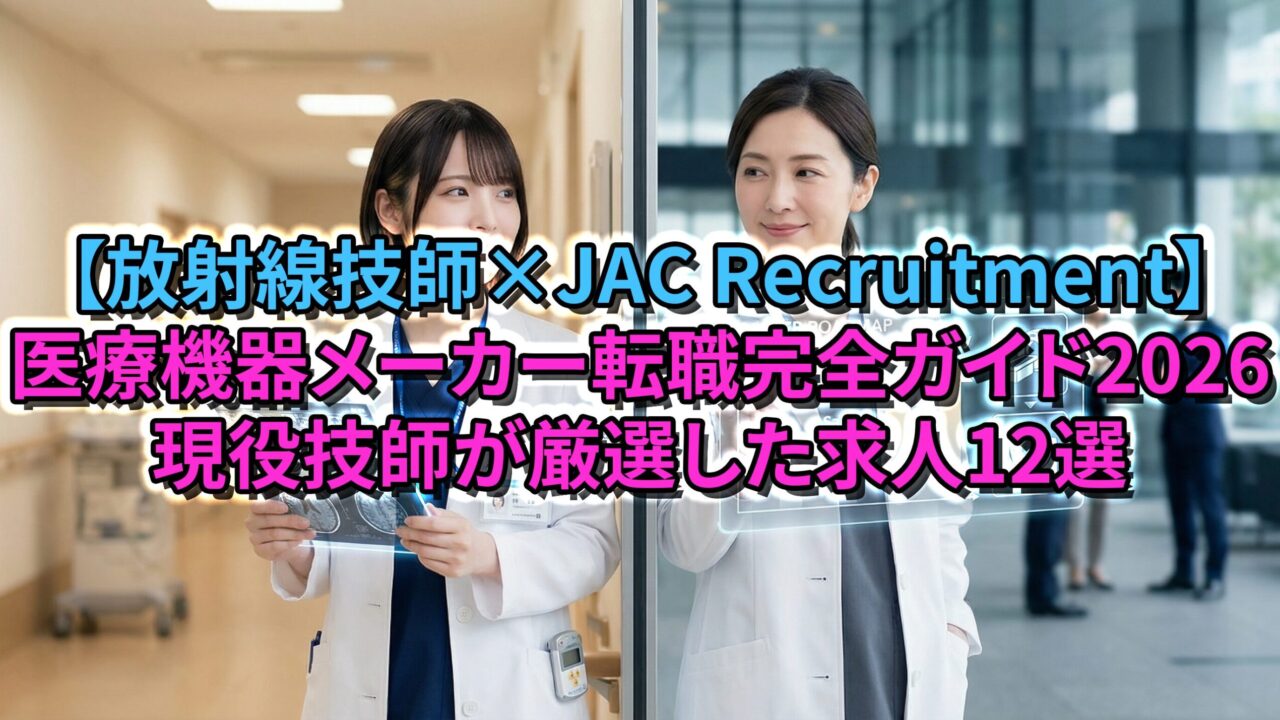
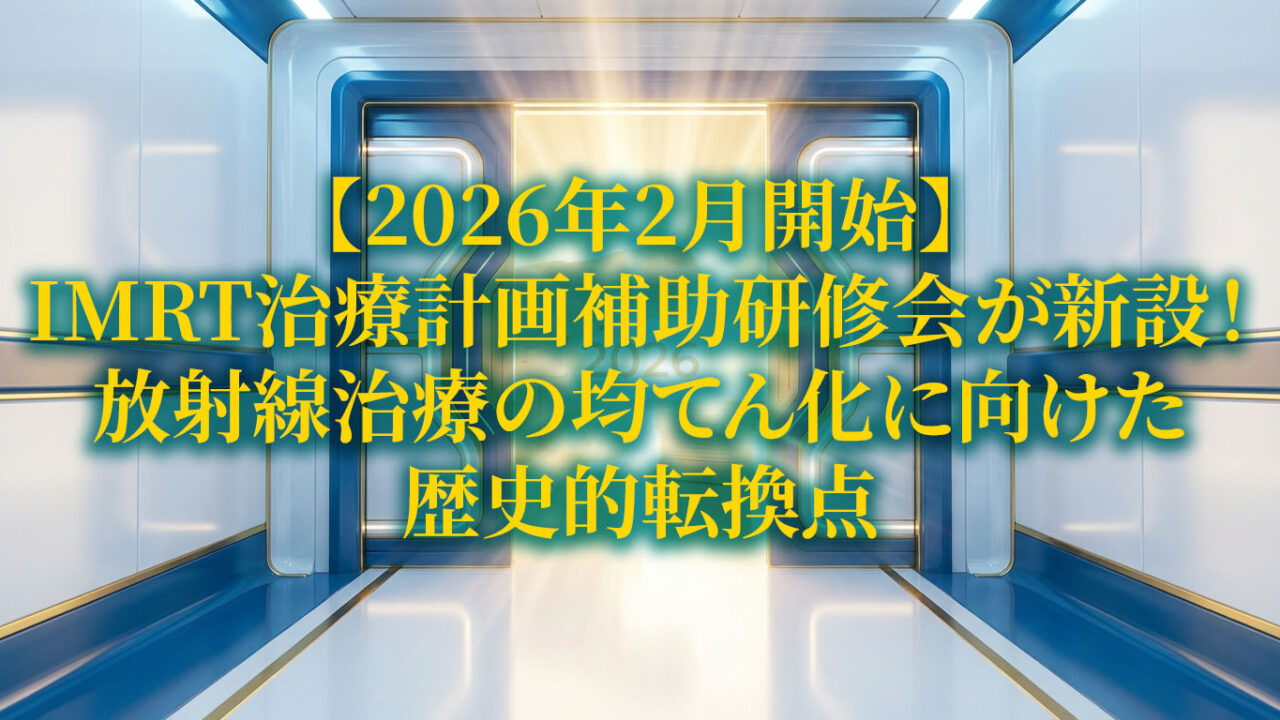
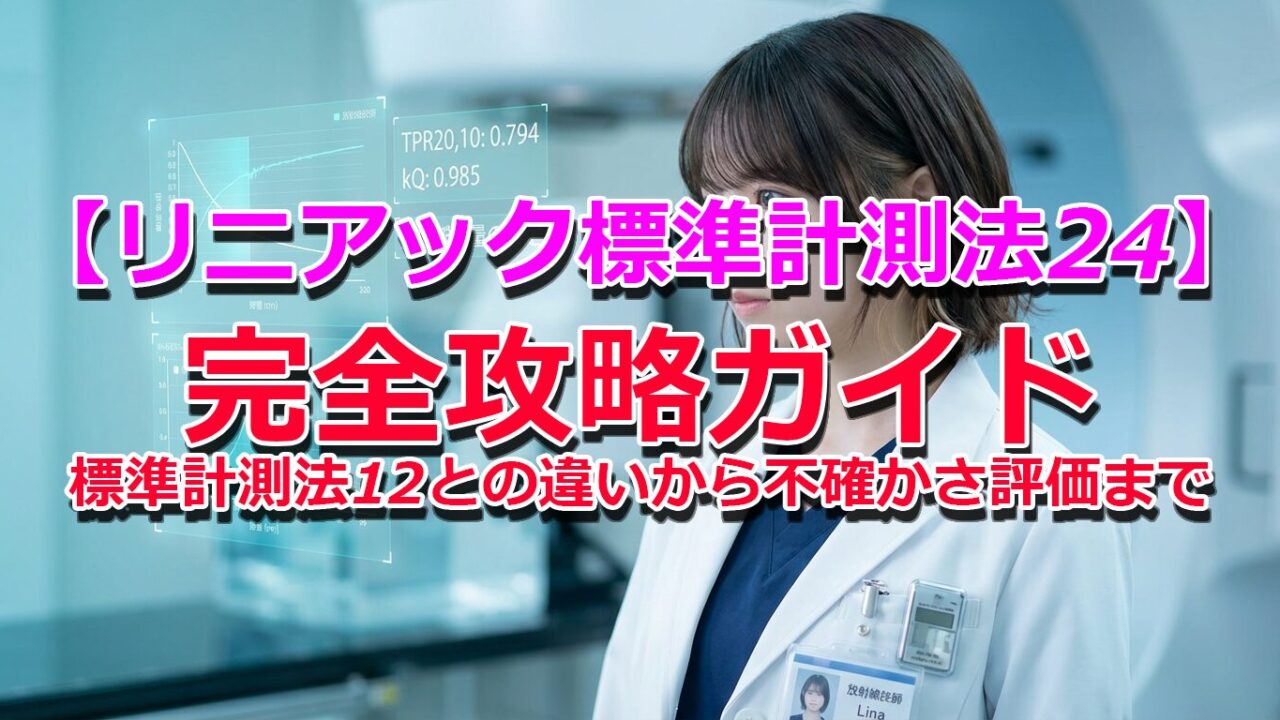
.jpg)