超音波検査士認定試験前日のプレチェック|10問で最終チェック
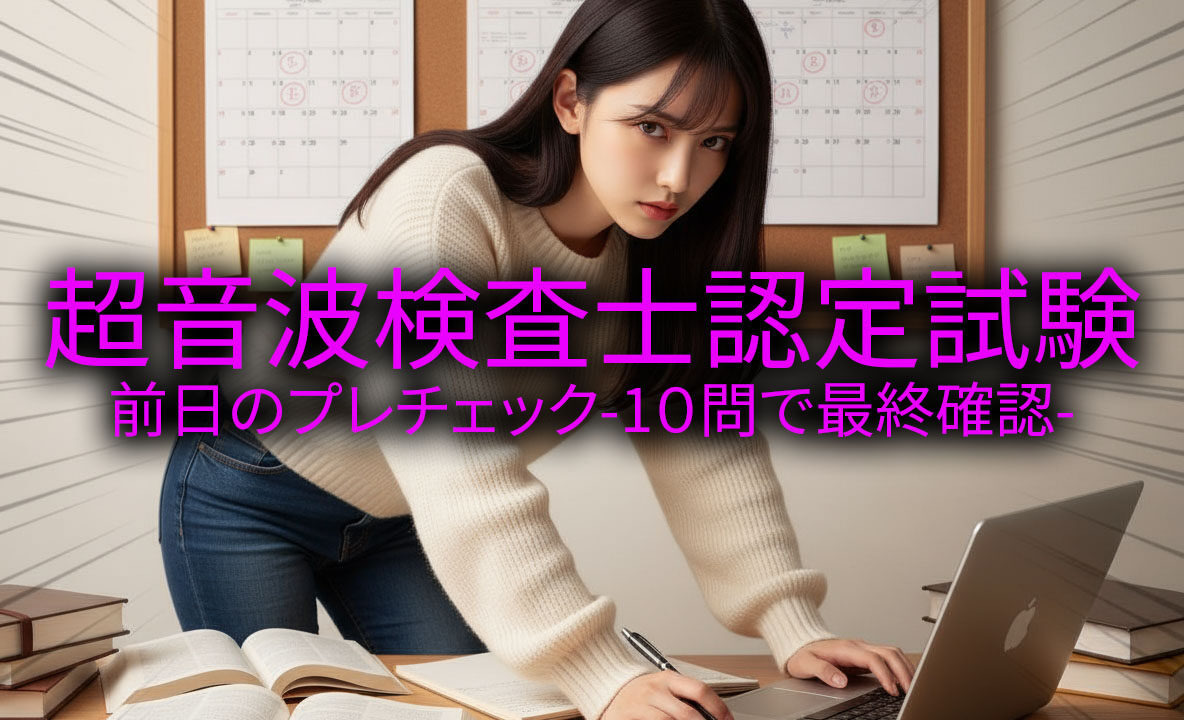
はじめに―明日が本番のあなたへ
いよいよ明日が超音波検査士認定試験本番ですね。今、この記事を読んでいるということは、もう十分に勉強してきたはず。でも「これで大丈夫かな?」「何か忘れていないかな?」と不安になっているかもしれません。
大丈夫です。その不安、めちゃくちゃよく分かります!
ここまで来たら新しいことを詰め込むより、これまで学んできたことを整理して、自信を持つことが大切です。
この記事では、試験前日に確認しておきたい重要ポイントを「10 問のプレチェック」形式でまとめました。サクッと解けたら自信になるし、もし忘れていた部分があっても、今なら間に合います。
それでは、一緒に最終チェックしていきましょう!
前日のメンタルセット
新しいことは勉強しない
これ、本当に大事です。うちの病院の先輩技師も口を酸っぱくして言ってました。前日に新しいテキストを開くのは厳禁。知らないことが出てきたら逆に不安になります。今日は「復習」だけにしましょう。
間違えた問題だけ見直す
過去問や問題集で間違えた問題にチェックを入れていますよね?その部分だけをパラパラと見返すのがベストです。「ああ、これ覚えたな」という確認作業で十分。
体調管理が最優先
当院の放射線部門では、国試や認定試験の前は「体調管理も実力のうち」と指導されます。特に超音波検査士試験は午前・午後通しての長丁場。風邪をひいていたら実力の半分も出せません。
- 早めに就寝(23 時までにはベッドに入る)
- 消化の良い食事(生ものは避ける)
- 手洗い・うがいの徹底
- 明日の天気と気温をチェック(服装の準備)
前日の10問プレチェック
それでは、本題の 10 問プレチェックに入ります。各領域から重要ポイントをピックアップしました。難易度は本試験レベルに設定していますので、しっかり考えてみてください。
問題: 超音波の伝播速度を1,540 m/sとしたとき、周波数5 MHzの超音波の波長はいくらか。
解答:約0.31 mm(308 μm)
解説:
波長 λ = 伝播速度 c ÷ 周波数 f
λ = 1,540 m/s ÷ 5,000,000 Hz = 0.000308 m = 0.308 mm
この計算、基礎編では頻出中の頻出です。伝播速度は軟部組織で約1,540 m/sと覚えておきましょう。周波数が高くなるほど波長は短くなり、分解能は向上しますが、到達深度は低下します。
現場の声: 一般的に、体表用に10 MHz以上の高周波プローブ、腹部用に3.5~5 MHz、心臓用に2.5~3.5 MHzを使い分けています。
問題: 超音波診断装置の分解能において、「距離分解能(軸方向分解能)」を向上させるために有効な方法を2つ挙げよ。
解答:
- 周波数を高くする(波長を短くする)
- パルス幅を短くする
解説:
距離分解能は、超音波ビームの進行方向に沿った分解能です。2つの反射体を別々に識別できる最小距離のことで、約1/2波長で決まります。
一方、方位分解能(横方向分解能)は、ビーム幅を狭くする、焦点を合わせる、高周波プローブを使用することで向上します。
現場での実感: 乳腺エコーで微小石灰化を見つける時、高周波プローブ(10~15 MHz)を使うと、本当に細かい構造まで見えます。ただし深部は見えにくくなるので、用途に応じた使い分けが重要です。
問題: 次のアーチファクトのうち、胆石や腎結石の診断に有用な所見として利用されるものはどれか。
a) 多重反射
b) 音響陰影
c) サイドローブアーチファクト
d) ミラーイメージ
解答:b) 音響陰影
解説:
音響陰影(Acoustic shadow)は、結石や骨など音響インピーダンスが大きく異なる物質で超音波が強く反射・吸収され、その後方に超音波が届かず黒く抜けて見える現象です。
胆石や腎結石では、この音響陰影が診断の重要な根拠となります。「強エコー+後方音響陰影」というセットで覚えましょう。
逆に、のう胞など液体成分が多いものは「後方エコー増強(posterior echo enhancement)」を示します。
現場での診断例: 当院で腹部エコーをしていると、「胆嚢内に高輝度エコー、体位変換で移動あり、後方音響陰影あり」→ 胆石と診断、という流れをよく経験します。この音響陰影がないと、胆泥(スラッジ)との鑑別が難しくなります。
問題: パルスドプラ法とカラードプラ法の特徴について、正しい記述はどれか。2つ選べ。
a) パルスドプラ法は、特定の部位の血流速度を定量的に測定できる
b) カラードプラ法は、血流の方向と速度を色で表現する
c) パルスドプラ法は、測定可能な最大血流速度に制限がない
d) カラードプラ法は、サンプルゲートを設定する必要がある
解答:a) と b)
解説:
- パルスドプラ法(PW: Pulsed Wave Doppler):サンプルゲートで指定した部位の血流を定量評価できますが、ナイキスト限界により高速血流の測定には限界があります(エイリアシングが発生)。
- カラードプラ法(Color Doppler):Bモード画像上に血流情報を色で重ね合わせて表示。赤色はプローブに近づく流れ、青色は遠ざかる流れを示すのが一般的です。
- 連続波ドプラ法(CW: Continuous Wave Doppler):高速血流の測定が可能ですが、深さ方向の分解能がありません。
現場での使い分け: 心エコーでは、僧帽弁逆流の評価にまずカラードプラで逆流を確認し、その程度をCWで定量評価する、というステップを踏みます。頸動脈エコーでは、狭窄部の血流速度上昇をPWやCWで測定します。
問題: 肝臓の超音波検査において、「脂肪肝」の典型的な所見として誤っているものはどれか。
a) 肝腎コントラストの増強
b) 深部エコーの減衰
c) 肝内血管の不明瞭化
d) 肝表面の凹凸不整
解答:d) 肝表面の凹凸不整
解説:
脂肪肝の典型的な超音波所見は:
- 肝実質エコーレベルの上昇(輝度増加)
- 肝腎コントラストの増強(腎臓より肝臓が明るく見える)
- 深部エコーの減衰(脂肪による超音波の吸収・散乱)
- 肝内血管の不明瞭化
一方、肝表面の凹凸不整は肝硬変の所見です。肝硬変では肝辺縁の鈍化・凹凸不整、肝実質の粗造化、脾腫などが見られます。
現場での経験談: 健診エコーでは脂肪肝は非常によく見ます。「先生、肝臓が腎臓より白く光ってますね」と声をかけると、生活習慣の見直しを促すきっかけになります。重度の脂肪肝では、本当に深部が見えにくくなって苦労します。
問題: 左室駆出率(LVEF: Left Ventricular Ejection Fraction)の基準値として、正常とされる範囲はどれか。
a) 30~40%
b) 40~50%
c) 50~70%
d) 70~90%
解答:c) 50~70%(一般的には55~70%)
解説:
LVEFは心臓のポンプ機能を表す最も重要な指標の一つです。
- 正常:55~70%(文献により50%以上とするものもあり)
- 軽度低下:45~54%
- 中等度低下:30~44%
- 高度低下:30%未満
計算式: LVEF (%) = (LVEDV – LVESV) / LVEDV × 100
※LVEDV:左室拡張末期容積、LVESV:左室収縮末期容積
現場での重要性: 当院の循環器内科では、心不全患者のフォローで必ずLVEFを測定します。「EF 30%以下で重症心不全」「EF 40%台で要注意」といった具合に、治療方針の決定に直結する重要パラメータです。
問題: 乳房超音波診断において、悪性を疑う所見として最も重要度が低いものはどれか。
a) 縦横比(D/W比)が1.0以上
b) 後方エコーの増強
c) 境界部の不整(スピキュラ)
d) 内部エコーの不均一性
解答:b) 後方エコーの増強
解説:
乳癌を疑う超音波所見(日本乳腺甲状腺超音波医学会「乳房超音波診断ガイドライン第4版」より):
悪性を強く疑う所見:
- 形状:不整形、分葉状
- 境界部:スピキュラ(棘状の突出)、境界不明瞭
- 内部エコー:不均一、低エコー
- 縦横比(D/W比):0.7以上(特に1.0以上)
- 後方エコー:減弱または変化なし
良性を示唆する所見:
- 形状:楕円形、円形
- 境界部:明瞭平滑
- 後方エコー:増強(のう胞など)
- 縦横比:0.7未満
現場での診断経験: 「境界不明瞭+スピキュラ+後方エコー減弱」の三拍子揃った腫瘤を見つけると、「これは要精査だな」となります。逆に「境界明瞭+後方エコー増強」なら線維腺腫やのう胞の可能性が高い。
問題: 頸動脈エコー検査において、内膜中膜複合体厚(IMT: Intima-Media Thickness)の測定部位と、動脈硬化の評価基準について、正しいものはどれか。
a) 総頸動脈の前壁で測定し、1.0 mm未満が正常
b) 総頸動脈の後壁で測定し、1.1 mm以上で肥厚と判定
c) 内頸動脈の分岐部で測定し、1.5 mm以上で狭窄あり
d) 外頸動脈の後壁で測定し、2.0 mm以上で要精査
解答:b) 総頸動脈の後壁で測定し、1.1 mm以上で肥厚と判定
解説:
IMTは動脈硬化の指標として重要です。
測定方法:
- 測定部位:総頸動脈(CCA)の後壁
- 測定範囲:頸動脈球部(分岐部)の1~2 cm中枢側
- 評価:拡張期の画像で測定
判定基準:
- 正常:1.0 mm以下
- 肥厚:1.1 mm以上
- プラーク:1.5 mm以上の限局性肥厚、または周囲のIMTより0.5 mm以上厚い部分
現場での測定: 当院の脳ドックでは、全例で頸動脈エコーを実施します。「IMT 1.2 mmで軽度肥厚、プラークなし」といった所見を記載します。特に糖尿病や高血圧の患者さんでは、経年的にIMTが増加していくのがよく分かります。
問題: 下肢静脈エコー検査において、深部静脈血栓症(DVT)を疑う所見として適切でないものはどれか。
a) 圧迫法で静脈が完全に虚脱しない
b) 静脈内に可動性のある高輝度エコーを認める
c) カラードプラで血流シグナルが欠損する
d) ミルキング操作で呼吸性変動が増強する
解答:d) ミルキング操作で呼吸性変動が増強する
解説:
深部静脈血栓症(DVT)の超音波診断所見:
陽性所見(血栓あり):
- 圧迫法(コンプレッション法)で静脈が完全に虚脱しない
- 静脈内に異常エコー(血栓)を認める
- カラードプラで血流シグナルの欠損・減弱
- 呼吸性変動の消失または減弱
正常所見:
- 圧迫で静脈が完全に虚脱する
- カラードプラで良好な血流
- 呼吸性変動あり(深呼吸で血流が変動)
- ミルキング操作(下腿を圧迫)で中枢側への血流増加
つまり、dの「呼吸性変動が増強する」は正常所見であり、DVTを疑う根拠にはなりません。
現場での経験: 整形外科の術後患者さんや、長期臥床の方でDVTチェックを行うことがあります。下腿の腫脹で来院され、「ヒラメ静脈に血栓あり、圧迫法陽性」と所見を出すと、即座にヘパリン投与開始、そんな場面もあるでしょう。
問題: 造影超音波検査(CEUS: Contrast-Enhanced Ultrasound)に使用される超音波造影剤の特徴として、正しいものはどれか。2つ選べ。
a) ヨード系造影剤である
b) マイクロバブル(微小気泡)を含む
c) 腎機能障害があっても使用できる
d) 血液脳関門(BBB)を通過する
解答:b) と c)
解説:
超音波造影剤(ソナゾイド®など)の特徴:
- 成分:マイクロバブル(直径2~3μmの微小気泡)を含む
- ヨード非含有:ヨードアレルギーの患者にも使用可能
- 腎排泄ではない:肺から呼気として排泄されるため、腎機能障害があっても使用可能
- 血管内に留まる:血液脳関門は通過しない
適応:
- 肝腫瘤性病変の質的診断(HCC vs 転移 vs 血管腫など)
- 乳腺腫瘤、膵腫瘤の評価
- 心筋コントラストエコー
現場での使用経験: 肝腫瘤の精査で造影USを行う場合があります。造影早期(動脈相)で濃染し、後期(平衡相)でwash outする病変は肝細胞癌を強く疑います。CT/MRIのヨード・ガドリニウム造影剤が使えない腎不全患者さんでも安全に使えるのが大きなメリットです。
前日の過ごし方―チェックリスト
10 問、お疲れさまでした!どうでしたか?すんなり解けた問題もあれば、「あれ?」と思った問題もあったかもしれません。でも大丈夫。間違えた部分を今サッと見直せば、明日には自分のものになっています。
さて、ここからは前日の実務的な準備をチェックしていきましょう。
☑️ 持ち物の最終確認
絶対に必要なもの:
- [ ] 受験票(最重要!顔写真の貼付確認)
- [ ] 本人確認書類(運転免許証、保険証など)
- [ ] HB 鉛筆(5 本以上)+鉛筆削り
- [ ] プラスチック消しゴム(2 個以上)
- [ ] 黒ボールペン
- [ ] 腕時計(スマートウォッチ不可、計算機能なし)
あると便利なもの:
- [ ] 飲み物(ペットボトル)
- [ ] 軽食(チョコレート、飴など)
- [ ] ティッシュ、ハンカチ
- [ ] 上着(会場の冷房対策)
- [ ] 耳栓(休憩時間の仮眠用)
- [ ] 常備薬(頭痛薬、胃腸薬など)
- [ ] マスク(予備も)
- [ ] 最小限の参考資料(間違いノートなど)
試験会場には時計がない場合もあります。必ず自分の腕時計を持っていきましょう。また、鉛筆は予想以上に消耗します。5 本は多いと思うかもしれませんが、実際には「足りなくて焦った」という先輩の声を聞いたことがあります。

☑️ 会場までの交通手段確認
- [ ] 試験会場の住所・アクセスを再確認
- [ ] 交通機関の時刻表チェック(平日/休日に注意)
- [ ] 所要時間+ 30 分の余裕を持った出発時刻設定
- [ ] 遅延・運休時の代替ルート検討
- [ ] 前泊が必要な場合はホテル予約確認
☑️ 体調管理の最終確認
- [ ] 22 ~ 23 時までに就寝
- [ ] 消化の良い夕食(生もの・脂っこいもの避ける)
- [ ] アルコール摂取を控える
- [ ] 手洗い・うがいの徹底
- [ ] 明日の天気予報確認
- [ ] 適切な服装の準備(重ね着推奨)
「試験前日はカツ丼」という験担ぎもいいですが、胃もたれするようなら避けましょう。大事な試験中にお腹が痛くなったら元も子もありません。
当日の心構え
朝のルーティン
- 余裕を持って起床:遅くとも試験開始 3 時間前には起きる
- 朝食は必ず食べる:脳のエネルギー源。バナナやおにぎりなど軽めで OK
- トイレは余裕を持って:会場についたらまずトイレの場所確認
- 深呼吸:緊張したら、ゆっくり深呼吸を 3 回
試験中のテクニック
- わからない問題は飛ばす:1 問に 3 分以上悩まない。全問に目を通すことが優先
- マークミス防止:5 問ごとに受験番号とマークがズレていないか確認
- 見直しの時間を確保:最後の 10 分は見直し時間として確保
- 午前の出来を引きずらない:「午前失敗したかも…」と思っても、午後で挽回できます
昼休みの過ごし方
- 軽く食べる(食べ過ぎ注意、眠くなります)
- 外の空気を吸う
- 参考書は最小限に(不安を煽るだけ)
- 15 分程度の仮眠もあり(スマホのアラーム設定忘れずに)
応援メッセージ
超音波検査士の資格は、決して簡単な試験ではありません。でも、ここまで頑張ってきたあなたなら、絶対に大丈夫です。
試験当日、会場には同じ目標を持った仲間がたくさんいます。みんな緊張しているし、みんな不安です。でも、それぞれが患者さんにより良い検査を提供したい、という熱い想いを持って集まっています。
あなたもきっと大丈夫。
明日は、これまでの努力を存分に発揮してきてください。リラックスして、自分を信じて、いつも通りの実力を出せば、きっと良い結果が待っています。
参考文献
本記事の作成にあたり、以下の文献・ガイドライン・資料を参考に作成しています。
学会ガイドライン
- 日本超音波医学会公益社団法人日本超音波医学会公式サイトhttps://www.jsum.or.jp/
- 超音波検査士制度、試験要綱、診断基準等
- 日本循環器学会(2021)「循環器超音波検査の適応と判読ガイドライン(2021 年改訂版)」JCS2021, 日本循環器学会/日本心エコー図学会 他https://www.j-circ.or.jp/cms/wp-content/uploads/2021/03/JCS2021_Ohte.pdf
- 日本乳腺甲状腺超音波医学会(2020)「乳房超音波診断ガイドライン(改訂第 4 版)」南江堂
- 日本消化器がん検診学会(2021)「腹部超音波検診判定マニュアル改訂版」日本消化器がん検診学会 超音波検診委員会
- 日本腎臓学会(2024)「腎障害患者におけるガドリニウム造影剤使用に関するガイドライン(第 3 版)」https://cdn.jsn.or.jp/data/guideline_nsf_20240520.pdf
- 日本医学放射線学会「造影剤の安全使用に関する情報(造影剤安全性委員会)」https://www.radiology.jp/member_info/zoueizai.html
教科書・問題集
- 日本超音波医学会 編(2024)「超音波検査士・超音波指導検査士認定試験問題集 第 5 版 Web 動画付」医歯薬出版株式会社https://www.ishiyaku.co.jp/search/details.aspx?bookcode=226920
- 東京超音波研究会 如月会(2021)「超音波検査士認定試験対策:基礎編:過去問分析~出題のポイントで学ぶ」
- 株式会社文光堂「循環器超音波検査士への最短コース」https://www.bunkodo.co.jp/
- メディカルビュー社(2022)「これから始める血管エコー 改訂第 2 版」https://www.medicalview.co.jp/
ブログ・体験記
- おのこブログ「超音波専門医認定試験で学ぶこと」(2024-2025)https://onoko-blog.com/us_study_2025-7-24/臨床検査技師による超音波検査の実践的情報
- くまのこ検査技師塾トピック「7 月中から始めたい超音波検査士認定試験対策!具体的な勉強計画を立てよう」https://kumanokoboy.com/blog/sayuko25/
- Kaeru Blog「超音波検査士の概要~取得までの流れ」https://kaerublog37.com/echo-20220209/
資格試験対策サイト
- 伊藤塾コラム「資格試験の効果的な勉強法 7 選」https://column.itojuku.co.jp/gyosei/method/shikaku-benkyouhou/
- STUDY HACKER「資格試験対策のスペシャリストが提唱。最短合格のための 4 つの期間の過ごし方」https://studyhacker.net/masato-kito-interview02
- 医師国家試験対策予備校メック「国試当日を万全に迎えるためのポイントと準備物」(2024)https://www.gomec.co.jp/column/benkyo_20250117/



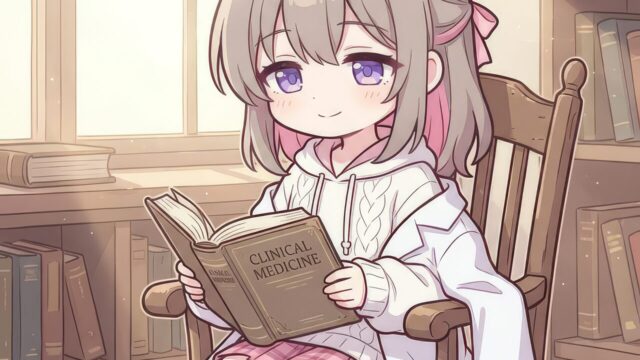



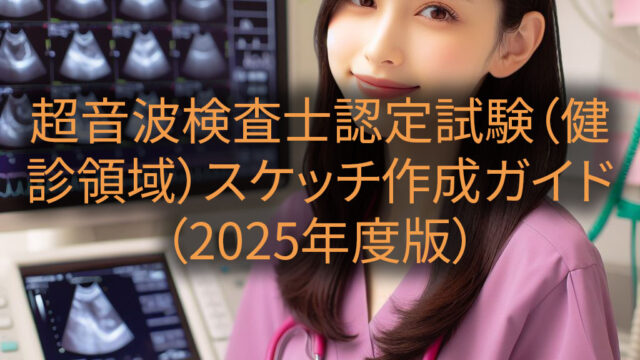





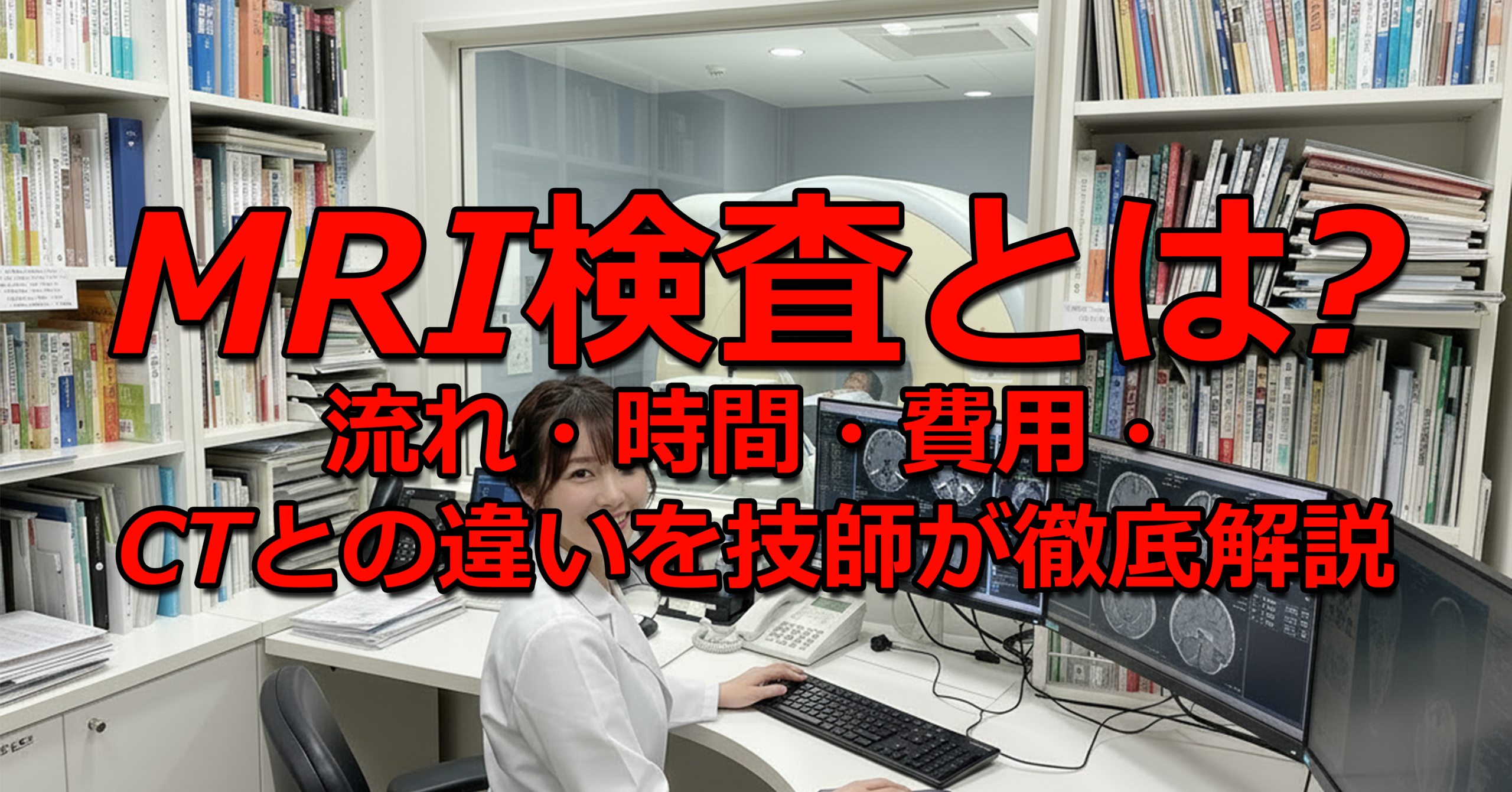
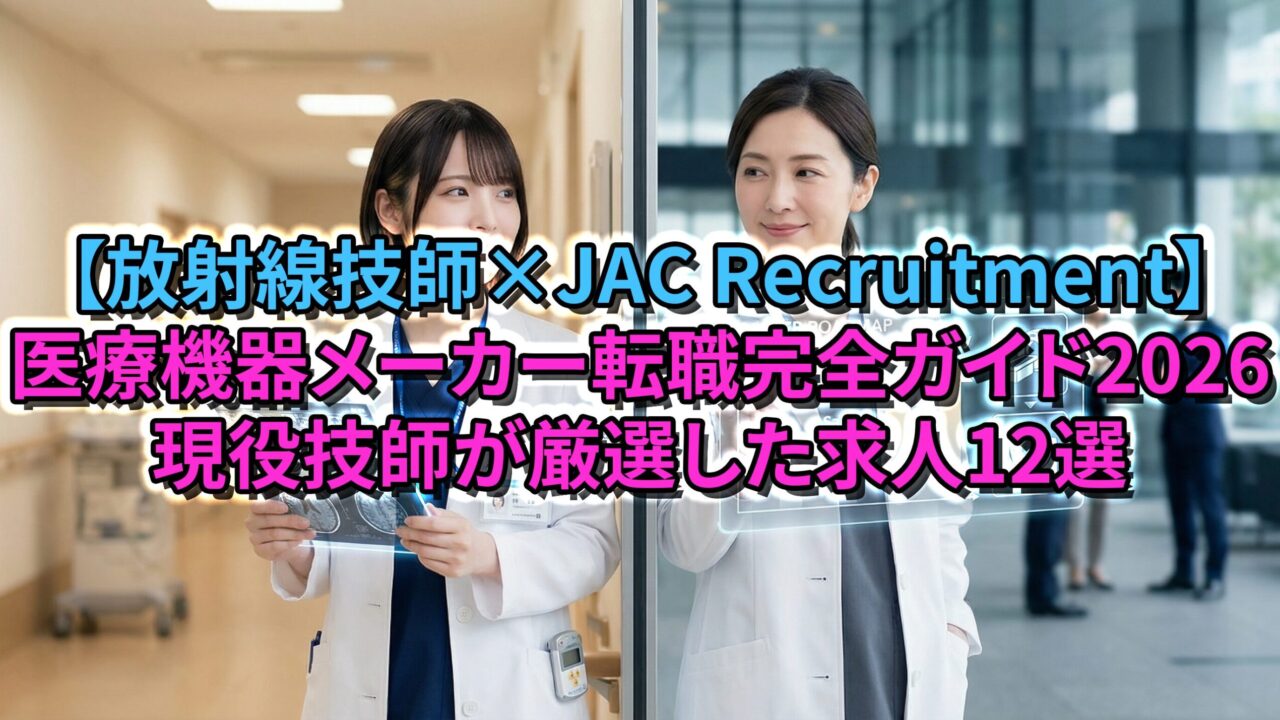
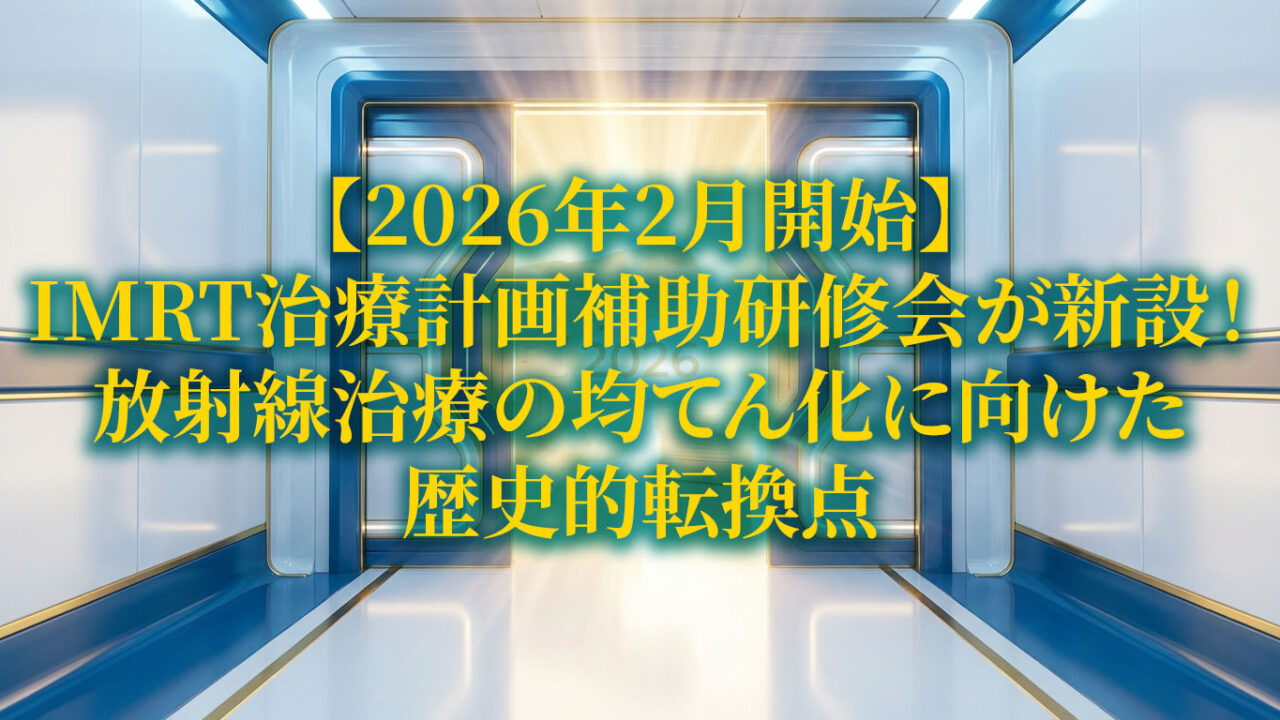
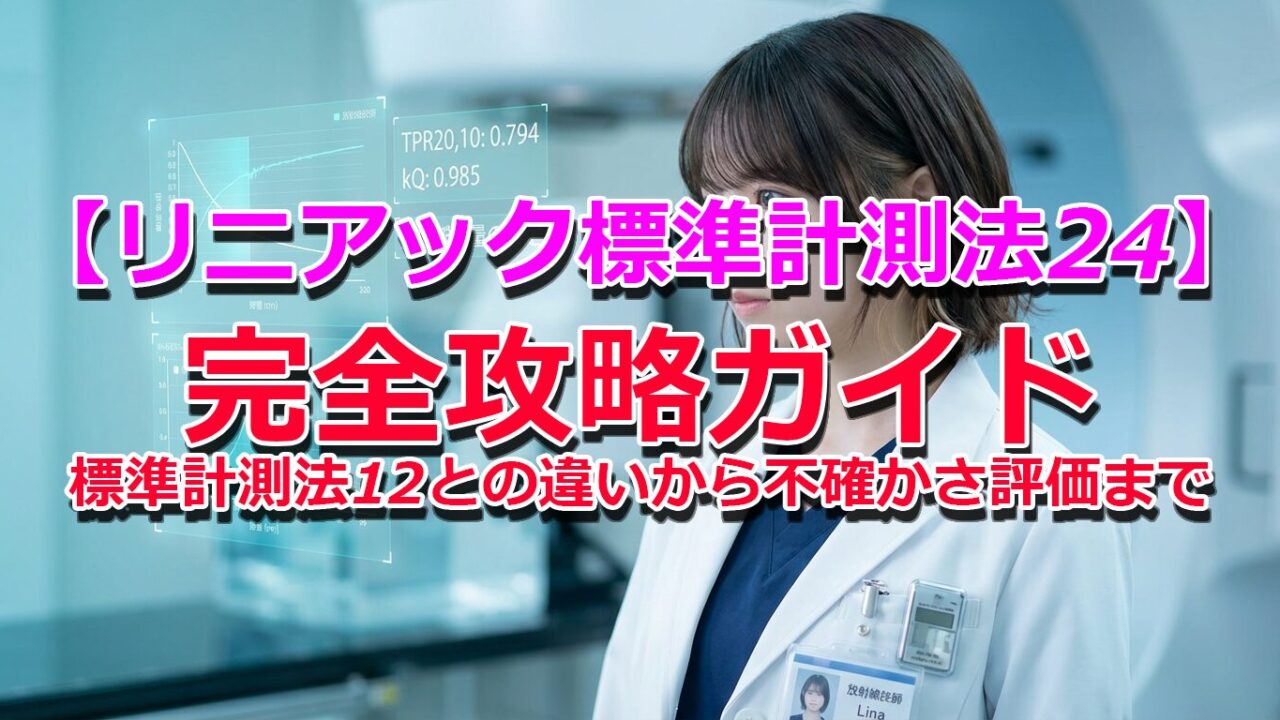
.jpg)