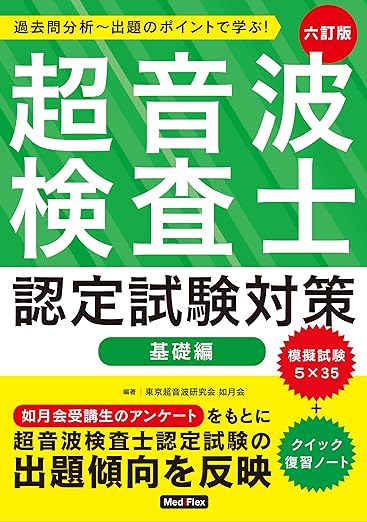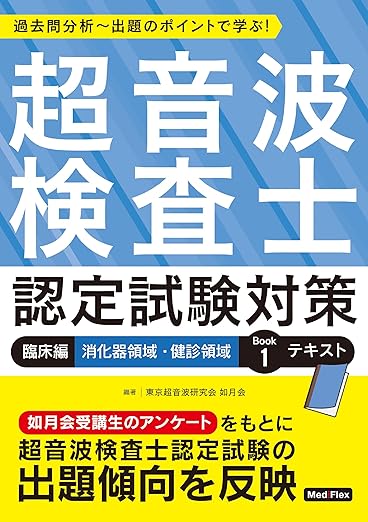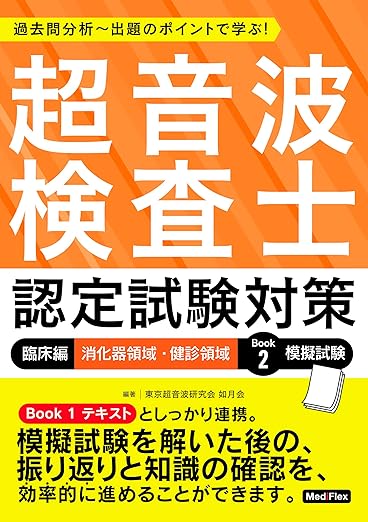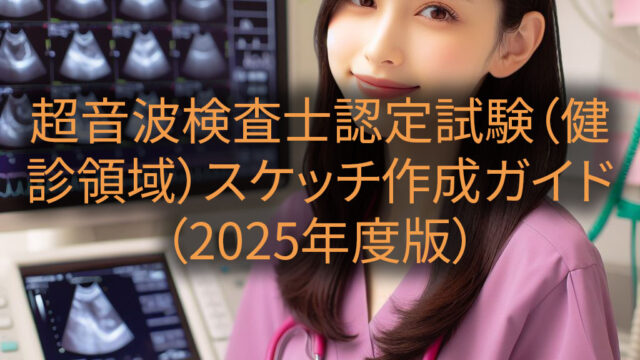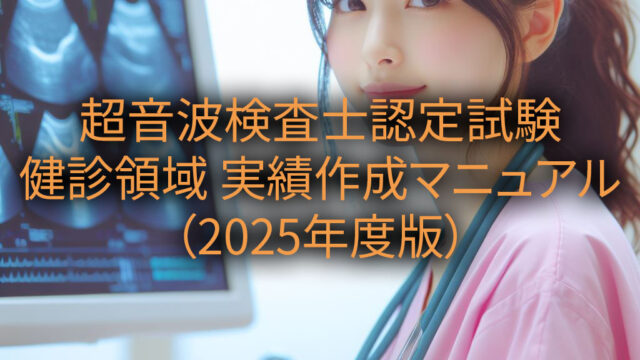この記事でわかること
- 試験直前に確認すべき重要ポイント30問
- 各問題の詳しい解説
- 間違えやすい問題の攻略法
- 試験当日の心構え
技師歴10年以上の筆者が、試験1週間前に絶対確認してほしい問題を厳選しました。
Contents
はじめに
超音波検査士認定試験まであと1週間。
この時期は「何を勉強すればいいかわからない」「不安で落ち着かない」という声をよく聞きます。
そこで、試験直前に確認すべき重要ポイントを30問にまとめました。
この問題集の使い方:
- まず全問解いてみる(答えを見ずに)
- 間違えた問題にチェックをつける
- 解説をじっくり読む
- 間違えた問題だけもう一度解く
全問正解できたら、自信を持って試験に臨んでください!
【基礎物理編】問題1-10
問題: 超音波検査で使用される周波数として、最も一般的な範囲はどれか。
a) 20Hz~20kHz
b) 100kHz~500kHz
c) 2MHz~15MHz
d) 50MHz~100MHz
解答:c) 2MHz~15MHz
解説:
人間の可聴域は20Hz~20kHzです。超音波はそれより高い周波数の音波を指します。
医用超音波検査では、2MHz~15MHzの範囲が一般的です。
- 腹部検査:2~5MHz(深部まで届く)
- 乳腺・甲状腺:7~12MHz(浅い部位を高解像度で)
- 血管・表在:10~15MHz(より高解像度)
覚え方: 「深い部位は低周波数、浅い部位は高周波数」
周波数が高いほど解像度は良くなりますが、減衰も大きくなるため深部まで届きません。
問題: 生体内における超音波の平均音速として、超音波診断装置で設定されている値はどれか。
a) 330m/s
b) 1,000m/s
c) 1,540m/s
d) 3,000m/s
解答:c) 1,540m/s
解説:
超音波診断装置は、生体内の平均音速を1,540m/sとして距離を計算しています。
これは水に近い音速です(水中は約1,500m/s)。
参考:他の媒質での音速
- 空気中:約330m/s
- 骨:約3,500m/s
- 脂肪:約1,450m/s
- 筋肉:約1,580m/s
生体内は組織によって音速が異なりますが、装置は1,540m/sで統一して計算しています。そのため、骨や脂肪が多い部位では若干の誤差が生じます。
試験頻出: 1,540m/sは必ず覚えてください!
問題: 周波数5MHzの超音波が生体内(音速1,540m/s)を伝播するとき、波長はおよそいくらか。
a) 0.3mm
b) 0.3cm
c) 3mm
d) 3cm
解答:a) 0.3mm(正確には0.308mm)
解説:
波長λは、λ = 音速 ÷ 周波数で計算します。
λ = 1,540m/s ÷ 5,000,000Hz
λ = 0.000308m
λ = 0.308mm ≒ 0.3mm
計算のコツ:
1,540を1,500として概算すると簡単です。
1,500 ÷ 5,000,000 = 0.0003m = 0.3mm
覚えておくべきポイント:
- 周波数が高い → 波長が短い → 解像度が良い
- 周波数が低い → 波長が長い → 深部まで届く
問題: 超音波ビーム方向(深さ方向)の分解能を向上させる方法として、適切なものはどれか。
a) 周波数を下げる
b) パルス幅を長くする
c) 周波数を上げる
d) ゲインを上げる
解答:c) 周波数を上げる
解説:
距離分解能(軸方向分解能)を向上させるには:
- 周波数を上げる → 波長が短くなる
- パルス幅を短くする → 近接した反射を分離できる
距離分解能 ≒ パルス幅の半分 ≒ 波長の半分
NG選択肢の理由:
- a) 周波数を下げる → 波長が長くなり、分解能が悪化
- b) パルス幅を長くする → 分解能が悪化
- d) ゲインを上げる → 分解能とは無関係(画像の明るさ)
試験のポイント: 「分解能を向上 = 周波数を上げる」は超音波の基本中の基本です。
問題: 超音波の減衰に関する記述で正しいのはどれか。
a) 周波数が高いほど減衰は小さい
b) 生体内では、1cmあたり約1dB/MHzの減衰が起こる
c) 骨は軟部組織より減衰が小さい
d) 減衰は距離に関係しない
解答:b) 生体内では、1cmあたり約1dB/MHzの減衰が起こる
解説:
生体内での超音波の減衰は、約0.5~1dB/cm/MHzです。
例:5MHzの超音波が10cm進むと
5MHz × 10cm × 1dB/cm/MHz = 50dB減衰
NG選択肢の理由:
- a) 周波数が高いほど減衰は大きい
- c) 骨は軟部組織より減衰が大きい
- d) 減衰は距離に比例する
実務での応用:
深部を観察する腹部エコーでは低周波数(2~5MHz)を使い、表在の甲状腺では高周波数(10~12MHz)を使うのはこのためです。
問題: 多重反射によるアーチファクトはどれか。
a) 音響陰影
b) 後方エコー増強
c) コメットサイン(リバーベレーション)
d) サイドローブアーチファクト
解答:c) コメットサイン(リバーベレーション)
解説:
多重反射(リバーベレーション)は、プローブと強い反射体の間で超音波が何度も往復することで発生します。
典型例:
- 胆嚢壁とプローブ間
- 横隔膜付近
- コメットサイン:彗星の尾のような線状エコー
他のアーチファクト:
- a) 音響陰影:胆石、骨などの後方が黒く抜ける
- b) 後方エコー増強:嚢胞性病変の後方が白く見える
- d) サイドローブ:メインビーム以外のビームによる偽像
見分け方: コメットサインは「尾を引くように深部まで続く線」です。
問題: ドプラ効果に関する記述で正しいのはどれか。
a) プローブに近づく血流は周波数が低くなる
b) プローブから遠ざかる血流は周波数が高くなる
c) ドプラ角度が90度のとき、最も正確に血流速度を測定できる
d) ドプラ角度が0度のとき、最も正確に血流速度を測定できる
解答:d) ドプラ角度が0度のとき、最も正確に血流速度を測定できる
解説:
ドプラ効果の基本:
- プローブに近づく血流 → 周波数が高くなる(赤色表示)
- プローブから遠ざかる血流 → 周波数が低くなる(青色表示)
ドプラ角度と測定精度:
血流速度 = ドプラ偏移周波数 ÷ (2 × 周波数 × cosθ) × 音速
cosθの値:
- θ = 0度 → cosθ = 1(最も正確)
- θ = 60度 → cosθ = 0.5(誤差が大きくなる)
- θ = 90度 → cosθ = 0(測定不可能)
実務のポイント: ドプラ角度は60度以下が推奨されています。
問題: フォーカス(焦点)に関する記述で正しいのはどれか。
a) フォーカスポイントより深部の方が、横方向の分解能が良い
b) フォーカスポイントで横方向の分解能が最も良い
c) フォーカスは距離分解能に影響する
d) フォーカスポイントを浅くすると、ビーム幅が広がる
解答:b) フォーカスポイントで横方向の分解能が最も良い
解説:
フォーカス(焦点)は、超音波ビームが最も細くなる位置です。
- フォーカスポイント = 横方向の分解能が最も良い位置
- フォーカスより浅い・深い部位 = ビームが広がり、分解能が低下
実務での応用:
観察したい部位(病変など)にフォーカスを合わせることで、最も鮮明な画像が得られます。
NG選択肢の理由:
- a) 深部はビームが広がり、分解能が悪化
- c) フォーカスは横方向の分解能に影響(距離分解能は周波数)
- d) フォーカスを浅くしても、ビーム幅は変わらない
問題: TGC(Time Gain Compensation:時間ゲイン補正)の目的として正しいのはどれか。
a) 深部の減衰を補正し、画面全体を均一な輝度にする
b) ノイズを除去する
c) 分解能を向上させる
d) フレームレートを上げる
解答:a) 深部の減衰を補正し、画面全体を均一な輝度にする
解説:
TGC(時間ゲイン補正)は、深さによって異なるゲイン(増幅率)をかけることで、減衰による輝度低下を補正します。
なぜ必要か?
超音波は深部に行くほど減衰するため、補正しないと深部が暗く見えてしまいます。
実務での使い方:
- 浅部のゲインを下げる
- 深部のゲインを上げる
- → 画面全体が均一な明るさになる
覚え方: 「TGC = 深さによってゲインを変える」
問題: フレームレートを向上させる方法として、適切でないのはどれか。
a) 表示深度を浅くする
b) 走査線密度を減らす
c) セクタ角度を狭くする
d) フォーカスポイントの数を増やす
解答:d) フォーカスポイントの数を増やす
解説:
フレームレートは、1秒間に何枚の画像を表示できるかを示します。
フレームレートを上げる(速くする)方法:
- 表示深度を浅くする → 走査時間短縮
- 走査線密度を減らす → 処理時間短縮
- セクタ角度を狭くする → 走査範囲縮小
フレームレートを下げる(遅くする)要因:
- フォーカスポイントを増やす → 処理時間増加
- 表示深度を深くする
- 走査線密度を増やす
実務のポイント: 心臓など動きの速い臓器では、フレームレートを上げて観察します。
【解剖・走査法編】問題11-20
問題: 肝臓を左葉と右葉に分ける解剖学的境界はどれか。
a) 肝鎌状間膜
b) 肝静脈(中肝静脈)
c) 門脈本幹
d) Cantlie線(カントリー線)
解答:d) Cantlie線(カントリー線)
解説:
肝臓の区分には2つの考え方があります:
1. 解剖学的区分(古い分類)
- 肝鎌状間膜で左葉・右葉に分ける
- 現在はあまり使われない
2. 機能的区分(Couinaud分類)
- Cantlie線(中肝静脈とIVC)で左葉・右葉に分ける
- 門脈支配に基づく8区域分類
- 現在の標準
Cantlie線: 胆嚢窩とIVCを結ぶ線
試験のポイント: 「機能的区分 = Cantlie線」は頻出です。
実務での応用: 腫瘍の位置を報告する際は、Couinaud分類(S1~S8)を使います。
問題: 胆嚢を最も観察しやすい体位はどれか。
a) 仰臥位
b) 左側臥位
c) 腹臥位
d) 立位
解答:b) 左側臥位
解説:
胆嚢の基本走査:
- 仰臥位 → まず基本像を描出
- 左側臥位 → 胆嚢が右側に移動し、観察しやすくなる
- 座位・立位 → 胆石が移動するか確認
なぜ左側臥位が良いか?
- 肝臓が右側に移動し、胆嚢が助間から出てくる
- 胃や腸のガスが移動し、観察の妨げにならない
- 胆石が移動性を確認できる
実務のコツ:
- 空腹時(絶食6時間以上)に行う → 胆嚢が拡張している
- 右肋間走査と右肋弓下走査を併用
問題: 腎臓の超音波像で正しい記述はどれか。
a) 腎実質エコーは肝実質より高エコー
b) 腎洞部は低エコー
c) 腎皮質は腎髄質より高エコー
d) 正常な腎盂は無エコー領域として描出される
解答:c) 腎皮質は腎髄質より高エコー
解説:
正常な腎臓のエコー像:
- 腎洞部:高エコー(脂肪組織が多い)
- 腎皮質:中等度エコー(肝実質とほぼ同じ)
- 腎髄質:低エコー(腎ピラミッド)
- 腎盂:正常では描出されない(水分がないため)
エコーレベルの順:
腎洞(高)> 腎皮質(中)> 腎髄質(低)
NG選択肢の理由:
- a) 腎実質エコーは肝実質とほぼ同じ
- b) 腎洞部は高エコー
- d) 正常な腎盂は描出されない(水腎症があれば無エコー領域として見える)
病的所見: 腎皮質が肝実質より高エコーになったら、腎実質障害を疑います。
問題: 成人の正常な脾臓の頭尾長(最大径)はおよそどれか。
a) 5cm以下
b) 10cm以下
c) 12cm以下
d) 15cm以下
解答:c) 12cm以下
解説:
正常脾臓のサイズ:
- 頭尾長:10~12cm
- 厚さ:3~5cm
- 体格で脾臓のサイズは異なるが、12cmを超えたら脾腫を疑う
測定方法:
左肋間走査で脾臓の最大長径を計測
脾腫の原因:
- 肝硬変(門脈圧亢進症)
- 血液疾患(白血病、悪性リンパ腫など)
- 感染症(EBウイルスなど)
実務のポイント: 「脾臓12cm以上 = 脾腫」と覚えてください。
問題: 膵臓を超音波で観察する際のランドマークとして最も有用なのはどれか。
a) 下大静脈
b) 腹部大動脈
c) 脾静脈
d) 上腸間膜動脈
解答:c) 脾静脈
解説:
膵臓走査の基本:
最重要ランドマーク = 脾静脈
- 脾静脈は膵体部・膵尾部の背側を走行
- 脾静脈を目印に膵臓を探す
- 「脾静脈の上にあるのが膵臓」
その他のランドマーク:
- 上腸間膜動脈(SMA):膵頭部と膵体部の境界
- 腹部大動脈:脾静脈よりさらに背側
- 下大静脈:膵頭部の右側
走査のコツ:
- まず腹部大動脈を描出
- その前方の脾静脈を探す
- 脾静脈の上が膵臓
実務のポイント: 膵臓は胃のガスで見えにくいことが多いので、飲水法や体位変換を活用します。
問題: 甲状腺の超音波像で正しいのはどれか。
a) 正常甲状腺は低エコー
b) 正常甲状腺は周囲筋より高エコー
c) 正常甲状腺の厚さは2cm以下
d) 甲状腺峡部は描出されない
解答:b) 正常甲状腺は周囲筋より高エコー
解説:
正常甲状腺のエコー像:
- エコーレベル:周囲筋(胸鎖乳突筋など)より高エコー
- 内部エコー:均一
- 被膜:薄い高エコーライン
- 各葉の厚さ:2cm以下
- 峡部:描出される(薄い)
エコーレベルの順:
甲状腺(高)> 周囲筋(低)
異常所見:
- 低エコー結節 → 腫瘍や嚢胞を疑う
- 全体的に低エコー + 粗雑 → 橋本病を疑う
- びまん性腫大 → バセドウ病を疑う
試験のポイント: 「正常甲状腺 > 周囲筋」のエコーレベル関係は頻出です。
問題: 乳腺超音波検査で推奨される走査法はどれか。
a) 放射状走査のみ
b) 同心円状走査のみ
c) 放射状走査と同心円状走査の併用
d) 横断走査のみ
解答:c) 放射状走査と同心円状走査の併用
解説:
乳腺超音波の基本走査:
1. 放射状走査:乳頭を中心に放射状に走査
- 乳管の走行に沿った走査
- 病変の検出に有用
2. 同心円状走査:乳頭を中心に同心円状に走査
- 放射状で見つけた病変の広がりを確認
- 乳管の連続性を評価
両方を併用することで見落としを防ぐ
実務のコツ:
- 時計の文字盤で位置を記録(3時方向、など)
- 乳頭からの距離も記載
- 微細石灰化にも注意
問題: 下肢深部静脈血栓症(DVT)の超音波診断で最も重要な所見はどれか。
a) 血流速度の低下
b) 圧迫法で静脈が虚脱しない
c) 血管壁の肥厚
d) 静脈弁の逆流
解答:b) 圧迫法で静脈が虚脱しない
解説:
DVT診断の基本:圧迫法(compression method)
正常静脈:
- プローブで圧迫すると完全に虚脱する
- 静脈内腔が見えなくなる
DVT(血栓あり):
- プローブで圧迫しても虚脱しない
- 血栓が静脈内に見える
- 非圧縮性(non-compressible)
その他の所見:
- 血栓エコー(低~等エコー)
- 血流シグナルの欠損
- 静脈の拡張
実務のポイント: 圧迫法は簡便で感度が高いため、DVT診断の第一選択です。
問題: 頸動脈超音波検査で測定するIMT(内膜中膜複合体厚)の基準値はどれか。
a) 0.5mm以下
b) 1.0mm以下
c) 1.5mm未満
d) 2.0mm未満
解答:b) 1.0mm以下
解説:
IMT(Intima-Media Thickness)の基準:
- 正常:1.0mm以下
- 肥厚:1.1mm以上
- プラーク:1.5mm以上の限局性肥厚
測定部位:
総頸動脈(CCA)の遠位壁を、長軸像で測定
IMT肥厚の意義:
- 動脈硬化の早期マーカー
- 心血管イベントのリスク予測
実務のコツ:
- 拡張期に測定(内腔が最も広い時期)
- 左右両側を測定
- 3回測定して平均値を採用
試験頻出: 「IMT 1.0mm以下が正常」は必須知識です。
問題: 心エコー検査で、左室長軸像を描出するアプローチはどれか。
a) 傍胸骨左縁長軸像
b) 傍胸骨左縁短軸像
c) 心尖部四腔像
d) 心窩部アプローチ
解答:a) 傍胸骨左縁長軸像(PLAX)
解説:
心エコーの基本4断面:
1. 傍胸骨左縁長軸像(PLAX)
- 左室の長軸を描出
- 左室、左房、大動脈、僧帽弁を観察
2. 傍胸骨左縁短軸像(PSAX)
- 左室を短軸(輪切り)で描出
- 弁レベル、乳頭筋レベルなど
3. 心尖部四腔像(A4C)
- 4つの心腔を同時に観察
- 左室、右室、左房、右房
4. 心窩部アプローチ
- 下大静脈、肝静脈を観察
- 右心系の評価
試験のポイント: 各アプローチで何が見えるか、整理しておきましょう。
【疾患・異常所見編】問題21-30
問題: 肝血管腫の典型的な超音波所見はどれか。
a) 境界不明瞭な低エコー腫瘤
b) 境界明瞭な高エコー腫瘤
c) 内部に壊死を伴う腫瘤
d) 辺縁に低エコー帯を伴う腫瘤
解答:b) 境界明瞭な高エコー腫瘤
解説:
肝血管腫の典型像:
- 境界明瞭で輪郭不整
- 高エコー(均一)
- 後方エコー増強あり
- 辺縁の低エコー帯なし
- 多発することもある
鑑別診断:
- 肝細胞癌:境界不明瞭、辺縁低エコー帯(halo)、モザイクパターン
- 転移性肝癌:境界明瞭、低エコー、bull’s eye sign
確定診断:
造影CT、造影MRIで特徴的な染まり方(早期濃染、後期持続)
実務のポイント: 肝血管腫は良性腫瘍で、経過観察が基本です。
問題: 胆石の超音波所見として正しくないのはどれか。
a) 高エコー
b) 音響陰影
c) 体位変換で移動性あり
d) 後方エコー増強
解答:d) 後方エコー増強
解説:
胆石の3徴候:
- 高エコー:石は音波をよく反射
- 音響陰影(acoustic shadow):石の後方が黒く抜ける
- 移動性:体位変換で重力方向に移動
NG選択肢の理由:
- d) 胆石は音響陰影を伴う(後方エコー増強ではない)
後方エコー増強が見られるもの:
- 嚢胞
- 胆嚢(内部が胆汁で液体)
鑑別診断:
- 胆嚢ポリープ:移動性なし、音響陰影なし
- 胆嚢腺筋腫症:壁内の小嚢胞(comet-like echo)
問題: 急性胆嚢炎の超音波所見として最も特異的なのはどれか。
a) 胆石の存在
b) 胆嚢壁の肥厚
c) Murphy’s sign陽性
d) 胆嚢の腫大
解答:c) Murphy’s sign陽性
解説:
急性胆嚢炎の超音波所見:
1. Murphy’s sign陽性(最も特異的)
- プローブで胆嚢を圧迫したときの疼痛
- 患者さんが痛がって息を止める(吸気を止める)
- 胆嚢壁の肥厚(3mm以上)
- 胆嚢の腫大
- 胆石の存在(約90%)
- 胆嚢周囲の液体貯留
なぜMurphy’s signが最も特異的か?
胆嚢壁肥厚や胆嚢腫大は、他の疾患(肝硬変、心不全など)でも見られますが、Murphy’s sign陽性は急性胆嚢炎に特異的です。
実務のポイント: Murphy’s signを確認する際は、必ず患者さんに「痛いですか?」と声をかけます。
問題: 脂肪肝の超音波所見として正しいのはどれか。
a) 肝臓のエコーレベルが腎臓より低い
b) 肝内血管の描出が明瞭になる
c) 深部エコーの減衰が強い
d) 肝表面が不整になる
解答:c) 深部エコーの減衰が強い
解説:
脂肪肝の超音波3徴候:
- Bright liver:肝臓が腎臓より高エコー
- 深部エコーの減衰:肝臓の深部が見えにくい
- 血管の不明瞭化:門脈や肝静脈の壁が不明瞭
正常との比較:
- 正常:肝実質エコー ≒ 腎実質エコー
- 脂肪肝:肝実質エコー > 腎実質エコー
NG選択肢の理由:
- a) 肝臓のエコーレベルが腎臓より高い
- b) 肝内血管の描出が不明瞭になる
- d) 肝表面の不整は肝硬変の所見
問題: 肝硬変の超音波所見として正しくないのはどれか。
a) 肝表面の凹凸不整
b) 肝辺縁の鈍化
c) 脾腫
d) 肝臓の腫大
解答:d) 肝臓の腫大
解説:
肝硬変の超音波所見:
- 肝表面の凹凸不整(nodular surface)
- 肝辺縁の鈍化
- 肝萎縮(特に右葉)← d)が誤り
- 肝内エコーの粗雑化・不均一
- 脾腫(門脈圧亢進症)
- 腹水
- 側副血行路の発達
NG選択肢の理由:
- d) 肝硬変では肝臓が萎縮する(腫大ではない)
- 肝腫大が見られるのは:急性肝炎、うっ血肝など
実務のポイント: 肝硬変の診断には、複数の所見を総合的に評価します。
問題: 腎結石の超音波所見として正しいのはどれか。
a) 腎盂内の高エコー、移動性あり
b) 腎盂内の高エコー、音響陰影あり
c) 腎盂の拡張
d) 腎皮質の菲薄化
解答:b) 腎盂内の高エコー、音響陰影あり
解説:
腎結石の超音波所見:
- 高エコー
- 音響陰影(acoustic shadow)
- 移動性なし(腎盂内で固定)← a)が誤り
cf. 胆石との違い:
- 胆石:移動性あり
- 腎結石:移動性なし
合併症:
- 水腎症:結石が尿管に詰まると、腎盂が拡張
- 腎盂腎炎:感染を合併
NG選択肢の理由:
- a) 腎結石は移動性なし
- c) 腎盂の拡張は水腎症の所見
- d) 腎皮質の菲薄化は慢性腎不全の所見
問題: 水腎症のgrading(重症度分類)で、腎盂・腎杯が拡張し、腎実質が軽度菲薄化している状態はどれか。
a) Grade 1
b) Grade 2
c) Grade 3
d) Grade 4
解答:c) Grade 3
解説:
水腎症のgrading(SFU分類):
- Grade 0:正常(腎盂拡張なし)
- Grade 1:腎盂のみ軽度拡張
- Grade 2:腎盂・腎杯が拡張(実質菲薄化なし)
- Grade 3:腎盂・腎杯が拡張 + 実質の軽度菲薄化
- Grade 4:高度拡張 + 実質の著明な菲薄化
原因:
- 尿管結石
- 尿管腫瘍
- 後腹膜線維症
- 妊娠(生理的水腎症)
実務のポイント: 水腎症を見つけたら、原因検索(CT、造影検査など)が必要です。
問題: 甲状腺癌を疑う超音波所見として最も重要なのはどれか。
a) 高エコー結節
b) 嚢胞性病変
c) 微細石灰化
d) 辺縁整な結節
解答:c) 微細石灰化(microcalcification)
解説:
甲状腺癌を疑う所見:
1. 微細石灰化(最も特異的)
- 砂粒体(psammoma body)を反映
- 乳頭癌に特徴的
- 低エコー結節
- 辺縁不整
- 前後径/横径 > 1(縦長、taller than wide)
- 内部血流豊富
良性を疑う所見:
- 高エコー
- スポンジ様(spongiform)
- 嚢胞性
- 辺縁整
- 粗大石灰化
実務のポイント: 微細石灰化を見つけたら、必ず穿刺吸引細胞診(FNA)を検討します。
問題: 乳癌を疑う超音波所見として正しくないのはどれか。
a) 不整形
b) 境界不明瞭
c) 後方エコー増強
d) 微細石灰化
解答:c) 後方エコー増強
解説:
乳癌を疑う所見:
- 不整形(spiculated margin:棘状)
- 境界不明瞭
- 低エコー
- 後方エコー減弱(癌細胞が音波を吸収)← c)が誤り
- 縦横比 > 1(taller than wide)
- 微細石灰化
良性腫瘍(線維腺腫など)の所見:
- 境界明瞭
- 整形(楕円形)
- 後方エコー増強または変化なし
- 縦横比 < 1
NG選択肢の理由:
- c) 乳癌は後方エコー減弱(増強ではない)
実務のポイント: 後方エコーの評価は、良悪性鑑別に重要です。
問題: 深部静脈血栓症(DVT)の好発部位として最も多いのはどれか。
a) 下腿の筋肉内静脈(ヒラメ筋静脈など)
b) 大腿静脈
c) 総腸骨静脈
d) 下大静脈
解答:a) 下腿の筋肉内静脈(ヒラメ筋静脈など)
解説:
DVTの好発部位(頻度順):
1. 下腿の筋肉内静脈(最多)
- ヒラメ筋静脈
- 腓腹筋静脈
- 遠位型DVT
- 膝窩静脈
- 大腿静脈
- 総腸骨静脈
- 下大静脈
臨床的重要性:
- 遠位型DVT(下腿):肺塞栓のリスクは低い
- 近位型DVT(膝窩静脈以上):肺塞栓のリスクが高い
実務のポイント: 下腿の筋肉内静脈は見落としやすいので、丁寧に圧迫法で確認します。
試験当日の心構え
1週間前にやるべきこと
✅ 知識の最終確認
- この30問を繰り返し解く
- 間違えた問題を重点的に復習
- 解剖図を見直す
✅ 体調管理
- 睡眠時間を確保(7~8時間)
- バランスの良い食事
- 風邪を引かないよう注意
✅ メンタルケア
- 適度な運動でリフレッシュ
- 過度な詰め込みは避ける
- 「できることはやった」と自信を持つ
試験当日
持ち物チェック:
- 受験票
- 筆記用具(HB鉛筆、消しゴム)
- 時計
- 身分証明書
時間配分:
- まず全問目を通す
- わかる問題から解く
- わからない問題は後回し
- 見直しの時間を確保
メンタル:
- 深呼吸してリラックス
- 最後まであきらめない
- 自分を信じる
さいごに
超音波検査士認定試験は、決して簡単な試験ではありません。
でも、ここまで勉強してきたあなたなら、必ず合格できます。
この30問で満点が取れたら、本番も大丈夫です。
試験当日は、落ち着いて、自分の力を信じて、全力を出し切ってください。
応援しています!
参考文献
関連記事
最終更新:2025年11月