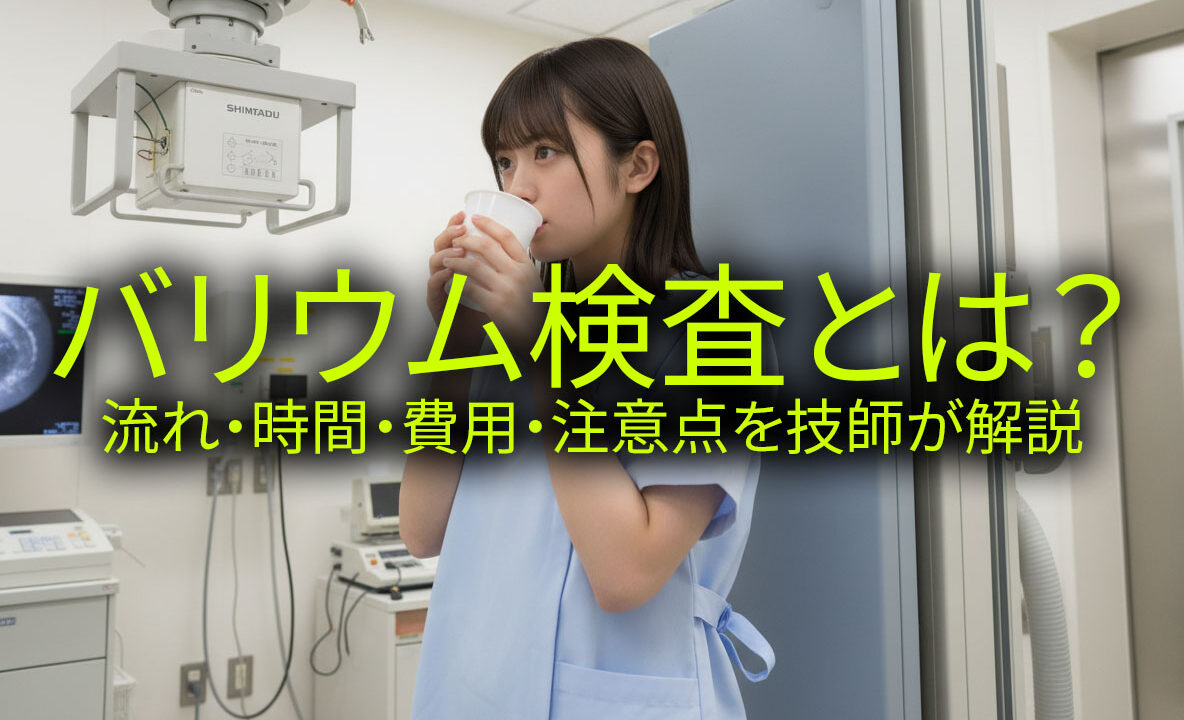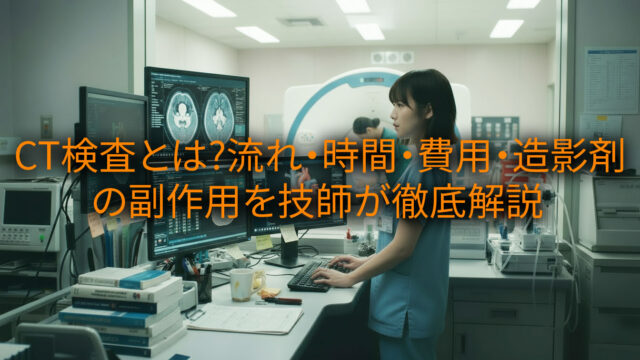この記事でわかること
- バリウム検査の基本的な仕組みと目的
- 検査の流れと所要時間
- 費用の目安(保険適用)
- 検査前後の注意点と下剤の重要性
- 胃カメラとの違いと使い分け
- よくある疑問への回答(便秘対策、副作用など)
放射線技師歴10年以上の筆者が、現場で毎日行っている検査について、患者さん目線で優しく解説します。
Contents
【結論】バリウム検査の基本情報まとめ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 正式名称 | 上部消化管造影検査(じょうぶしょうかかんぞうえいけんさ) |
| 検査時間 | 3〜7分(準備含めて15〜20分) |
| 痛み | なし(体を回転させる動きあり) |
| 費用(3割負担) | 単純検査:2,000〜3,000円 健診:自治体により異なる |
| 服装 | 検査着に着替え(金属類すべて外す) |
| 食事制限 | 前日21時以降絶食 当日朝も絶食 |
| 被ばく | あり(0.6mSv/回) |
| 年間受診者数 | 約1,000万人(日本) |
バリウム検査とは
バリウム検査は、白い造影剤(硫酸バリウム)と発泡剤を飲んで、X線で食道・胃・十二指腸を撮影する検査です。
最大の特徴
- 二重造影法 → バリウム(白)と空気(黒)のコントラストで粘膜の凹凸を描出
- 非侵襲的 → 体に管を入れないので苦痛が少ない
- スクリーニングに適する → 短時間で全体像を把握できる
体位変換のタイミングとバリウムの付着具合で画像のクオリティが大きく変わります
検査で分かる病気
- 胃がん – 診断精度70〜80%、死亡率を約40%減少
- 胃潰瘍・十二指腸潰瘍
- 胃ポリープ
- 慢性胃炎・急性胃炎
- 食道がん
- 食道静脈瘤
主な検査対象者
- 40歳以上の健康診断受診者(自治体検診)
- 胃の不調がある方(医師の判断)
- 胃がん検診を希望される方
検査の流れ
1. 検査前日・当日の準備
前日(検査の12時間前〜)
- 21時(または22時)までに夕食を済ませる
- それ以降は絶食
- 水分は適度に摂取可能(施設により異なる)
当日朝
- 絶食を継続
- 飲水も控える(少量の水で内服薬を飲むのはOKな場合が多い)
- 服薬中の方は事前に医師に相談
2. 受付・問診(5分)
- 問診票の記入
- 便秘の有無の確認
- 妊娠の可能性の確認(女性のみ)
- 過去の検査でのトラブル確認
3. 着替え(5分)
金属のない検査着に着替えます。
外す必要があるもの
- ネックレス、ピアス、指輪などのアクセサリー
- 腕時計
- ヘアピン(金属製)
- 入れ歯(金属を含む場合)
- メガネ
- ベルト
- ブラジャー(ワイヤー入り)
- 湿布、カイロ
4. 検査室入室(2分)
検査台の上に立ちます。このとき、少し緊張する方が多いですが、私たち技師がしっかりサポートしますのでご安心ください。
5. 発泡剤の服用(30秒)
最初に飲むのが発泡剤(粉薬または顆粒)です。これを少量の水で飲むと、胃の中で炭酸ガスが発生し、胃が風船のように膨らみます。
ポイント:ゲップを我慢!
- 発泡剤を飲んだ後、ゲップをしたくなりますが、できるだけ我慢してください
- ゲップをすると胃がしぼんで良い画像が撮れません
- どうしても我慢できない場合は技師に伝えてください
ゲップがこみ上げたら唾を飲み込むと少し楽になるみたいです
6. バリウムの服用(1分)
次に白いバリウム液(約200〜250ml)を飲みます。
最近のバリウムの特徴
- 味が改良されている(バニラ、イチゴ風味など)
- どろっとした感触(飲むヨーグルトより少し重い)
- 高濃度製剤で少量でも描出良好
7. 撮影と体位変換(3〜7分)
ここが私たち放射線技師の腕の見せどころです。
撮影のざっくりした流れ
- バリウムを飲み込む時 → 食道を観察
- 仰向け → 胃の後壁を観察
- うつ伏せ → 胃の前壁にバリウムを付着
- 右向き → 胃の小弯側を観察
- 左向き → 胃の大弯側を観察
- 斜め45度 → 十二指腸を観察
- 立位 → 胃全体の形を観察
- 腹部を圧迫 → 胃の粘膜を詳しく観察
各ポジションで5〜10秒程度静止していただき、合計10〜12枚程度の画像を撮影します。
撮影中の技師からの指示例:
- 「右に体を向けてください」
- 「息を吸って、止めてください」
- 「そのまま動かないでください」
- 「力を抜いてリラックスしてください」
実は技師側も結構大変です。患者さんの安全を確保しながら、最適なタイミングで撮影ボタンを押す。1日30〜40人撮ると、腰にきます…
8. 検査終了・着替え(5分)
撮影が終わったら、検査台から降りて着替えます。
超重要:下剤を必ず受け取る! 検査終了時に下剤を渡されます。これは絶対に飲み忘れないでください。
下剤を使用することによってバリウムが腸内に滞留してしまうのを防ぎます
所要時間
| 工程 | 時間 |
|---|---|
| 受付・問診 | 5分 |
| 着替え | 5分 |
| 発泡剤・バリウム服用 | 2分 |
| 撮影(健診) | 3〜5分 |
| 撮影(詳細検査) | 5〜7分 |
| 着替え | 5分 |
| 合計 | 20〜30分 |
ポイント
- 混雑状況により待ち時間が発生する場合があります
- 体を動かしにくい方は時間がかかる場合があります
- 撮影中に動いてしまうと撮り直しになり、時間が延びます
費用
保険適用の場合(3割負担)
| 検査内容 | 費用の目安 |
|---|---|
| バリウム検査(医療機関) | 2,000〜3,000円 |
| 胃X線検査(人間ドック追加) | 3,000〜5,000円 |
| 自治体の胃がん検診 | 500〜2,000円 |
| 自治体検診(無料対象年齢) | 無料 |
※費用は医療機関や自治体によって異なります
費用に含まれるもの
- 撮影料
- バリウム・発泡剤の薬剤費
- 画像診断料(読影料)
- 下剤
年間受診者数
日本全国で約1,000万人が毎年バリウム検査を受けています(2010年データでは約243万人が自治体検診で受診)。
検査後のケア【最重要】
バリウム検査で一番大切なのは、実は「検査後」です。検査そのものよりも、検査後のケアが不適切だと重大なトラブルにつながる可能性があります。
下剤の服用(絶対に忘れずに!)
服用タイミング:
- 検査直後、帰宅前に1回目を服用
- 帰宅後、6時間経っても排便がない場合は追加服用
下剤の種類: 多くの施設では酸化マグネシウムやセンノシド系の下剤が処方されます。
授乳中の場合母乳に成分が移行する可能性があるので、センノシドは避けましょう
水分摂取
目標:いつもの1.5倍
- 検査当日は通常より500ml〜1L多めに水分を摂取
- お水、麦茶、ほうじ茶がおすすめ
避けるべき飲み物:
- アルコール(利尿作用があり脱水の原因)
- コーヒー、緑茶(カフェインによる利尿作用)
- 炭酸飲料(ガスで腹部膨満感)
食事
検査後すぐに食事OK
- 消化の良いものから始める
- 食物繊維を多く含む食品がおすすめ
おすすめ食品:
- ごはん、うどん
- 野菜(キャベツ、ほうれん草など)
- 海藻類(わかめ、ひじき)
- 果物(バナナ、りんご)
- ヨーグルト
避けるべき食品:
- 脂っこいもの(揚げ物、ラーメンなど)
- 辛いもの
- 極端に冷たいもの
運動
軽い運動が効果的:
- 10〜20分程度の散歩
- 腸の蠕動運動を促進
排便の確認
正常な経過:
- 下剤服用後4〜6時間で効果が現れる
- 最初の便は白っぽい(バリウムが混ざっている)
- 2〜3回で徐々に通常の色に戻る
24時間以内に排便がない場合: → 医療機関に連絡
3日経っても白い便が続く場合: → 医療機関を受診
検査後の合併症(まれ)
軽度:
- 便秘(最も多い)
- 腹部膨満感
- 吐き気
重度(極めてまれ):
- 腸閉塞(10万人に数件)
- 消化管穿孔(10万人に数件)
厚生労働省の報告(1954年以降)では、消化管穿孔等27例(うち死亡4例)、ショック18例が報告されています。年間受診者約1,750万人(2004年度)から考えると、発生率は非常に低いですが、ゼロではありません。
現場で30年以上働いている先輩技師でも、重篤な合併症は「1回見たことがあるかないか」レベル。でも、だからこそ下剤と水分摂取が超重要です
胃カメラとの違い
5秒でわかる比較表
| 項目 | バリウム検査 | 胃カメラ(内視鏡) |
|---|---|---|
| 正式名称 | 上部消化管造影検査 | 上部消化管内視鏡検査 |
| 原理 | X線とバリウムのコントラスト | カメラで直接観察 |
| 被ばく | あり(0.6mSv) | なし |
| 診断精度 | 70〜80% | 90%以上 |
| 検査時間 | 3〜7分 | 5〜15分 |
| 苦痛度 | 少ない(体を回転) | 中〜大(喉の違和感) |
| 費用 | 2,000〜3,000円 | 3,000〜5,000円 |
| 組織検査 | できない | 可能(生検) |
| 検査後 | 下剤必須 | 特になし(鎮静剤使用時は安静) |
| 得意な病変 | スキルス胃がん、全体像の把握 | 早期がん、色調変化 |
エビデンスに基づく比較
胃がん死亡率減少効果:
日本のデータ:
- バリウム検査:約40%減少(日本消化器がん検診学会)
韓国の大規模調査(25万人対象):
- 胃カメラ:47%減少
- バリウム検査:2%減少
がん発見率:
- 早期胃がん:胃カメラが圧倒的に優位
- スキルス胃がん(浸潤型):バリウム検査の方が発見しやすい場合がある
どちらを選ぶべき?
バリウム検査がおすすめの方:
- 初めての胃がん検診
- 症状がない方のスクリーニング
- 胃カメラに抵抗がある方
- 短時間で済ませたい方
胃カメラをおすすめする方:
- 胃の症状がある方
- バリウムで異常が見つかった方
- 家族に胃がんの方がいる
- ピロリ菌除菌後の方(色調変化型の早期がんを見逃さないため)
- 50歳以上の方
迷ったら → 医師に相談してください。年齢、症状、家族歴などから最適な方法を提案してもらえます
個人的には「両方やるのが一番」と言いたいところですが、費用や時間の問題もありますよね。最近は胃カメラの鎮静剤(寝てる間に終わる)も進化してるので、選択肢としてありだと思います
よくある質問
まとめ
バリウム検査は、日本の胃がん検診を長年支えてきた重要な検査です。
覚えておきたいポイント:
- ✅ 短時間で食道・胃・十二指腸を観察できる
- ✅ 苦痛が少ない(体を回転させるだけ)
- ✅ 費用が比較的安い(3割負担で2,000〜3,000円)
- ✅ 胃がん死亡率を約40%減少させる効果あり
- ✅ 検査後の下剤と水分摂取が超重要
- ✅ 前日21時以降は絶食
- ✅ ゲップは我慢する
- ✅ 便秘がちな方は事前に相談
- ✅ 24時間以内に白い便が出ることを確認
私たち放射線技師からのメッセージ:
毎日何十人もの患者さんのバリウム検査を担当していますが、不安そうな顔で来られた方が「思ったより楽でした」と笑顔で帰られるのを見ると、とても嬉しくなります。
技師によって撮影技術に差があるのは事実です。だからこそ、私たちは日々研修や勉強会で技術を磨いています。大手医療機関では年間13万件以上の検査を行い、約30名の専門技師がチームで対応しています。
検査に不安があれば、遠慮なく私たちに声をかけてください。「ゲップが我慢できないかも」「体を動かすのがつらい」など、何でも相談していただければ、できる限り対応します。
胃がんは早期発見で治る病気です。
定期的な検査で、大切な体をしっかりチェックしていきましょう。
理解度チェッククイズ
参考文献
ガイドライン・学会資料
- 日本消化器がん検診学会「胃がん検診マニュアル 2025年改訂第3版」
- バリウム検査の標準的な手技と安全基準
- 2025年6月発行
- 日本消化器がん検診学会 HP
- 日本医学放射線学会「画像診断ガイドライン 2021年版」
- 上部消化管造影検査の適応と実施方法
- 日本医学放射線学会 HP
- 日本医学放射線学会「造影剤安全性委員会報告」
- 硫酸バリウム製剤の安全使用指針
- 造影剤安全性情報
- 厚生労働省「医薬品・医療機器等安全性情報」
- バリウム検査における副作用報告(1954年以降のデータ)
- 消化管穿孔等27例、ショック18例の報告
- 厚生労働省 HP
- 国立がん研究センター「がん情報サービス 胃がん検診」
- 検診の有効性に関するエビデンス
- がん検診受診率統計
- 国立がん研究センター HP
学術論文・書籍
- 「新・胃X線撮影法ガイドライン 改訂第4版」日本消化器がん検診学会編(医学書院)
- バリウム検査の撮影技術の標準化
- 体位変換の詳細な手技
- 二重造影法の理論と実践
- 「消化器画像診断アトラス」(医学書院)
- バリウム検査画像の読影ポイント
- 正常解剖と病的所見の比較
- 「これならわかる!消化管X線検査」(医学教育出版社)
- 技師や研修医向けの入門書
- 実践的な撮影テクニック
海外資料
- American College of Radiology「ACR Appropriateness Criteria」
- 米国における上部消化管造影の適応基準
- ACR 公式サイト
- Radiology: “Upper Gastrointestinal Series: Indications, Techniques and Safety”
- 国際的な標準手技の解説
統計データ出典
- 宮城県対がん協会
- 年間13万5千件の検査データ
- 専門技師約30名による実施体制
- 宮城県対がん協会 HP
- 慶應義塾大学病院 医療・健康情報サイトKOMPAS
- 消化管X線造影検査の詳細解説
- KOMPAS
安全性関連
- 日本放射線技術学会「医療被ばくガイドライン」
- 胃X線検査の標準的被ばく線量(0.6mSv)
- 日本放射線技術学会 HP
- 医療安全推進者ネットワーク「判決事例No.159」
- バリウム検査後の合併症に関する医療訴訟事例
- 下剤不投与による消化管穿孔のケース
製剤情報
- KEGG MEDICUS「硫酸バリウム製剤添付文書」
- 硫酸バリウム散99.1%、99.5%の製剤情報
- 禁忌、副作用、使用上の注意
- KEGG MEDICUS
関連記事: